今日は2025年8月15日、終戦から80年という節目の日です。
毎年この日を迎えるたびに、教師として、そして一人の人間として、子どもたちに何を伝えるべきか深く考えさせられます。「戦争はいけないことだ」「喧嘩をしてはいけない」――。これらの正論を教えることはもちろん重要です。しかし、ただ「戦争は絶対にいけない」と教えるだけで、果たして十分なのでしょうか。
私は、子どもたちに「なぜ平和は尊いのか」「どうすれば平和を守れるのか」という問いを、自分自身で深く考えてほしいと願っています。
戦争の歴史から目を背けず、多面的に考えることこそが、本当の意味で平和を守る力になると信じているからです。
歴史から学ぶ「なぜ戦争は起きるのか」
小学校では、6年生の社会科で日本の歴史を学びます。その中でも、近代史は非常に重要な単元です。しかし、学校の授業では、時間の都合で駆け足になってしまいがちです。
私はこの近代史を、子どもたちの「問い」を起点にじっくりと扱いたいと考えています。
- なぜ戦争は起きるのか?
- なぜ多くの人が犠牲になったのか?
- 今の平和は、誰の犠牲の上に成り立っているのか?
こうした問いに子どもたちが向き合うためには、まず彼ら自身が歴史的事実を知る必要があります。知識がなければ、深い問いは生まれません。だからこそ、教師として、子どもたちが自ら問いを立てられるように導いていくことが大切だと感じています。
【日本の近代史と戦争の道のり】
日本の近代史は、1868年の明治維新から始まります。鎖国を解き、富国強兵を掲げて近代化を急いだ日本は、日清戦争や日露戦争を経て国際的な地位を高めていきました。しかし、その過程で、大陸への権益拡大や資源確保を巡って他国との対立が深まっていきます。
特に、1931年の満州事変以降、国際連盟からの脱退、日中戦争の長期化、そして太平洋を挟んだアメリカとの対立が深まり、1941年には太平洋戦争へと突入しました。
この戦争は、日本の国土の多くを焦土と化し、広島と長崎への原子爆弾投下、そして沖縄での激しい地上戦など、多くの民間人の命を奪いました。最終的に、日本は1945年8月15日にポツダム宣言を受諾し、長い戦争の歴史に幕を下ろしました。
この歴史を学ぶことは、決して「日本が悪かった」という自虐的な歴史観に終始するべきではありません。むしろ、日本人として、当時の人々がどのような状況で、何を信じて行動したのかを深く考えることで、同じ過ちを繰り返さないための教訓を得ることが重要です。
「戦争は絶対いけない」だけでは不十分な理由
「戦争は絶対いけない」という言葉は、私たち大人が子どもに伝えるべき正論です。しかし、この言葉だけで思考を停止させてしまうのは危険だと感じています。
なぜなら、この世界から紛争や対立がなくなることはないからです。
私は、子どもたちにこう問いかけることがあります。
「もし、自分の家に悪者が突然押し入ってきて、家族が危険な目にあったとしたら、あなたは家族を守るために戦いませんか?」
この問いに対して、多くの子どもたちは「戦います」と答えます。大切な家族を守るために、戦うことは当然だと考えるからです。
では、この「家族を守るための戦い」が、「国を守るための戦い」、つまり「戦争」になったとき、何が違うのでしょうか。
「戦争は絶対にいけない」と教えられた子どもたちは、ここで考え込んでしまいます。
- 国を守るための戦争は、家族を守るための戦いと何が違うのだろう?
- そもそも「国」とは何だろう?「主権」とは何だろう?
- 本当に日本は戦争に一切関わっていないと言えるのだろうか?
こうした問いに答えを出すことは簡単ではありません。しかし、答えが出ないからこそ、子どもたちは自分自身で深く考え、様々な情報を集め、多角的な視点を持つことの重要性を学びます。
日本国憲法と「平和主義」
小学校では、社会科で日本国憲法についても学びます。憲法には、私たちが「平和主義」を掲げる国であるということが明確に記されています。
【日本国憲法と平和主義】
日本国憲法の前文には、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人類の平和を愛する」と書かれています。
そして、第9条では、戦争の放棄と戦力の不保持を定めています。
日本国憲法 第9条
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この憲法9条を学ぶとき、子どもたちには「ただ戦争をしないと決めている」と教えるだけでなく、さらに一歩踏み込んで考えてほしいと思っています。
- 「戦争をしない」と決めるだけで、本当に国を守れるのだろうか?
- 平和を守るために、私たちはどのような行動をとるべきなのだろうか?
こうした問いは、道徳の授業でも議論できるテーマです。子どもたちは、これらの議論を通して、単純な「正解」がない問題に向き合い、答えを導き出すための思考力を養っていきます。
戦争の記憶と、私たちにできること
先日、介護の仕事をしている知人から、印象的な話を聞きました。
その知人が働く介護施設に、認知症で普段は何も思い出せない97歳になる女性がいました。ある日、知人が何気なく「終戦から80年になるのですね」と話したところ、その女性は突然、ハラハラと涙を流し始めたというのです。
戦争は、それほどまでに人の心に深い傷を残す、決して忘れてはならない出来事です。
私たちは、終戦から80年という歳月が、戦争の記憶を風化させてしまうことを恐れなければなりません。しかし、ただ「戦争は悲惨だった」と教えるだけでは、子どもたちはその本当の意味を理解することは難しいでしょう。
私たちは、戦争の記憶を持つ人々のリアルな声に耳を傾け、日本の安全保障の現状や国際社会の動きなど、様々な情報を多角的・多面的に考える機会を子どもたちに与えなければなりません。
平和を守るための真の「主体性」
「平和を守るためにはどうすればいいのか」
この問いに対する答えは、誰かに教えてもらうものではありません。
私は、子どもたちが、与えられた情報を鵜呑みにせず、自分の頭で考え、判断し、行動できる人間に育ってほしいと願っています。
なぜなら、ただ「戦争はダメだ」と何も考えずに周りに流されてしまう人が多い社会は、何かきっかけがあれば、あっという間に戦争へと向かってしまう危険性があるからです。
真の平和とは、多様な情報を基に、自分で考え、自分の意思で守り抜くものです。
終戦80年という節目を迎え、改めてこのことを強く感じています。これからも子どもたちが「自分で考える力」を育めるよう、全力を尽くしていきたいと考えています。

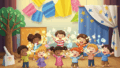

コメント