今回は、小学校の社会科で実践している「貿易ゲーム」の具体的な内容や教育効果を詳細にお伝えするとともに、ご家庭で親子一緒に楽しめる学習系ボードゲームをいくつかご紹介します。ぜひ、お子さんとの新しい学びの時間を創造するヒントにしてください。
ゲームを通じて社会の仕組みを「体感」する
私が小学校5年生の社会科で取り入れているのが「貿易ゲーム」です。このゲームは、単に知識を暗記するのではなく、貿易という複雑な仕組みを子どもたちが肌で感じられる、とても効果的な体験型学習法です。
日本の社会科では、日本の産業や外国との関わりについて学びます。一般的な授業では、日本の主要な輸出国や輸入国を調べ、資料から情報を読み取るといった学習が中心になりがちです。しかし、それだけでは、子どもたちは「知識」として知ることはできても、貿易が持つ本当の意味や、その裏側にある国際社会の現実を「実感」として理解するのは難しいのが現状です。
例えば、「日本は資源が少ない国だから、多くの資源を外国から輸入している」という事実。あるいは、「輸入した資源を国内で加工し、付加価値を付けて輸出する」という加工貿易の仕組み。これらの概念は、言葉で説明するだけでは、なかなか子どもの心に深く響きません。
そこで、私は貿易ゲームを通して、子どもたちにこの複雑な貿易の仕組みを「自分ごと」として捉えてもらうことを目指しています。
貿易ゲームの具体的な進め方
貿易ゲームは、クラス全体をいくつかのチーム(国)に分け、それぞれに異なる状況を与え、そこから物語が始まります。
- チーム(国)分けと初期設定: クラスの子どもたちを5〜6人のグループに分け、それぞれを一つの「国」と設定します。日本のように30人から35人程度のクラスであれば、だいたい6つのチームに分かれることになります。
- 資源と技術力の差: 各チームに封筒を1つずつ配ります。この封筒の中身が、その国が持つ「資源」と「技術力」を表しています。
- 技術力も資源も豊富な国: 切れ味の良いハサミ、定規、コンパスといった道具(高い技術力)と、A4用紙(資源)が大量に入っています。この国は、自国だけで多くの製品を作れる恵まれた国です。
- 資源はあるが技術力がない国: 大量のA4用紙は入っているが、道具はほとんど入っていない、もしくは切れ味の悪いハサミしかない、といった設定です。資源はあるものの、それを製品に変える力がありません。
- 資源はないが技術力がある国: 日本を想定した国で、A4用紙は1枚も入っていませんが、高性能な道具が揃っています。技術力は高いものの、資源を他国に頼らざるを得ない状況です。
- 資源も技術力もない国: A4用紙が1枚しか入っていないなど、ほとんど何も入っていない封筒を渡されます。いわゆる発展途上国を想定した設定です。
- ゲームスタート: 先生は子どもたちに「封筒の中身を開けて、指定された形(例えば、正方形や三角形など)を作り、銀行役の先生に売ってください。ただし、正確に作らないと買い取りません」とだけ伝えます。
子どもたちは封筒を開け、自分たちの置かれた状況を初めて知ります。しばらくの間は、恵まれたチームがスムーズに作業を進める一方で、資源や技術力のないチームは「どうしよう…」と途方に暮れます。
しかし、ここからがこのゲームの面白いところです。しばらくすると、子どもたちは他チーム(他国)との交渉を始めます。資源のない国は、資源のある国に「紙をいくらで売ってくれる?」と持ちかけ、技術力のない国は、技術力のある国に「ハサミを貸してほしい」と頼みます。
そうした交渉の中で、子どもたちは自然と「貿易」というものがどういうことなのかを体感していきます。交渉が上手くいかなかったり、資源を独占しようとするチームがあったり、さまざまなドラマが生まれます。最終的に各チームの利益を発表してゲームは終了しますが、そこで終わりではありません。
この貿易ゲームは、**開発教育協会(DEAR)**などの団体によって制作・提供されている、教育現場で広く使われている教材です。貿易ゲームについてさらに詳しく知りたい方は、開発教育協会のウェブサイトなどを参考にしてみてください。
貿易ゲームが育む、多角的な「力」
貿易ゲームの真価は、単に社会科の知識を学ぶことにとどまりません。このゲームは、子どもたちの人間力や思考力を多角的に育む、非常に奥深い教育ツールです。
1. 教科の枠を超えた深い学び
ゲーム後の振り返りの時間が最も重要です。子どもたちは、ゲームの体験を通して、以下のような深い問いを自分自身に投げかけます。
- 貿易と貧富の差: 「どうして僕たちの国は、こんなにお金持ちになれたんだろう?」逆に「どうしてあの国は、ほとんど利益を出せなかったんだろう?」といった疑問から、貿易の不均衡や国の置かれた状況について考えます。
- 産業廃棄物と環境問題: ゲーム中に紙くず(ゴミ)が大量に出ます。そこで「このゴミはどうする?」という問いを投げかけることで、産業活動における環境問題や、持続可能な社会のあり方について考えさせます。
- 国際協力: 利益を上げた国が、そうでない国に無償で資源や技術を提供する場面も出てきます。この体験から、国際協力の必要性や、国際機関の役割について自然と学ぶことができます。
このように、貿易ゲームは、社会科の概念的な学習を、子どもたちの体験と結びつけることで、ただの知識ではない、生きた知恵に変えてくれます。
2. 複雑な人間関係を乗り越える力
高学年になると、子どもたちの人間関係は複雑になりがちです。しかし、貿易ゲームは、そうした人間関係に良い影響を与えます。
ゲーム中は、普段はあまり話すことのない子と協力して交渉したり、戦略を練ったりする必要が出てきます。こうした協働作業を通して、「あの子は意外と交渉がうまいんだな」「〇〇くんと協力したら、こんなに上手くいった!」といった発見が生まれます。
ゲームという非日常的な体験が、子どもたちの間に自然なコミュニケーションを生み、クラスの一体感を高める効果があるのです。
3. 勉強だけでは測れない才能の開花
貿易ゲームは、いつもテストの点数が高い子だけが活躍するわけではありません。
むしろ、交渉が苦手だったり、戦略を立てるのが得意でなかったりする子もいれば、逆に普段はあまり目立たない子が、交渉役として素晴らしい才能を発揮したり、チームをまとめるリーダーシップを見せたりすることが多々あります。
このゲームを通して、子どもたちは「勉強ができる」という一面的な価値観ではない、多様な才能や強みを発見することができます。テストの点数では見えないその子の「すごさ」に、クラスの仲間が気づくことで、子どもたちの自己肯定感も高まり、クラス全体の雰囲気がポジティブに変わっていくのです。
家庭でもできる!親子で楽しむ学習ゲーム
家庭で上述の貿易ゲームをするのは難しいかもしれませんが、家庭でも気軽に、親子で楽しめる学習系のボードゲームはたくさんあります。
ここでは、単なる遊びで終わらず、子どもの思考力やコミュニケーション能力が自然と育まれる、おすすめのボードゲームを2つご紹介します。
- カタン (Catan)
- 概要: 無人島を開拓しながら、資源を交換・取引して自分の街を広げていくボードゲームです。交渉や戦略を立てる力が身につきます。
- 学べること: 資源の価値、交渉術、計画性など、経済の仕組みを遊びながら体感できます。親子で「今、この木材を売るべきか?」といった会話をすることで、自然と論理的思考力が養われます。
- リンク: カタン スタンダード版
- モノポリー (Monopoly)
- 概要: 有名な不動産ボードゲームです。土地を買い占め、ホテルを建てて、他のプレイヤーから賃料を徴収しながら資産を増やしていきます。
- 学べること: お金の流れ、投資、戦略的思考など。金融教育の第一歩として、お金の価値や経済の仕組みを学ぶことができます。親子で「なぜこの土地を買ったの?」「ホテルを建てるタイミングは?」といった会話をすることで、子どもの金銭感覚を育てることができます。
- リンク: モノポリー クラシック
親子で一緒にルールを理解し、戦略を練り、協力し、時には交渉することで、子どもたちは教科書だけでは学べない、生きた知恵と力を身につけていきます。ゲームを使った教育実践について、またご紹介していきたいと思います。
社会科と関連した国語力向上の実践についてはこちら↓

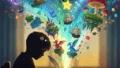
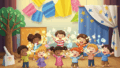
コメント