近年、高校や大学入試で小論文が課されることが増えています。入試だけではなく、社会に出てからも自分の考えを整理し、発信する力は大事なスキルです。また、書くことは思考を深め、自分自身と向き合うための大切な手段でもあります。
しかし「書くこと」を「つまらない」「難しい」と感じている子は多いです。子どもたちが楽しみながら書く力を伸ばしていくために、「作家の時間」という学習法を実践しています。どのようなものか、そしてご家庭でできる具体的な取り組みをお伝えします。
作家の時間とは? 子どもが「作家」になる学習法
「作家の時間」とは、アメリカで生まれた「ライティング・ワークショップ」を日本の子どもたちに合わせてアレンジしたものです。
作家の時間: 「書く」ことが好きになる教え方・学び方実践編 (シリーズ・ワークショップで学ぶ) | プロジェクト ワークショップ |本 | 通販 | Amazon
この学習法では、子どもたちが「自分は作家だ!」という意識を持ち、書きたいテーマを自分で選び、読者を意識しながら構成を考え、自由に文章を書いていきます。
この活動を通して、子どもたちは「何を」「どのように」書くかを自分で決める自己選択・自己決定を繰り返します。学校の授業では、どうしても教師主導で進むことが多いですが、作家の時間では子どもが主役です。この主体性が、受け身ではない「自ら学ぶ力」を育みます。また、テーマを考え、構成を練り、表現を工夫する過程で、学習指導要領で求められている「思考力」「判断力」「表現力」といった力が自然と身についていくのです。
作家の時間には、大きく分けて3つの要素があります。
- ミニレッスン: 先生が短い時間で、文章の書き方や構成のヒントを伝えます。例えば、「文章の書き始めのいくつかのパターン」や、「読者が情景を想像しやすいような言葉の選び方」など、実践的で具体的なテクニックを学びます。
- 執筆と個別指導: 子どもたちがそれぞれのテーマで執筆する時間です。先生は一人ひとりの席を回り、個別にアドバイスをします。この個別指導は「カンファランス」と呼ばれ、子どもたちの進捗や悩みに寄り添う大切な時間です。
- 分かち合い(シェアリング): 自分の作品を友達に発表したり、感想を伝え合ったりする時間です。自分の作品を誰かに読んでもらう喜びを知ることで、子どもたちの書く意欲はさらに高まります。
これらのサイクルを毎週繰り返すことで、子どもたちは無理なく、着実に書く力を伸ばしていきます。
作家の時間の効果:なぜ子どもは「書くこと」が好きになるのか
「作家の時間」を続けることで、子どもたちには次のような変化が現れます。
1. 書くことが「楽しい!」に変わる
多くの場合、学校の授業では、教科書の単元に沿って「〜について書きなさい」と、テーマや文字数が決められています。これでは、「やらされている」感覚が強くなってしまい、書くことそのものが苦手になってしまう子どもも少なくありません。
しかし、「作家の時間」では、子どもたちが自分で書きたいテーマを自由に選び、書くことができます。例えば、「好きなゲームの攻略法」「飼っているペットの面白い行動」など、子どもたちの興味関心は多岐にわたります。自分の「好き」をテーマにすることで、書くことが楽しいと感じられるようになり、文章を書くことへの抵抗感がなくなっていくのです。これが、書く力を伸ばす上で最も重要な第一歩だと言えるでしょう。
2. 毎週「書く時間」を確保できる
教科書に沿った学習では、書く単元が終わると、数ヶ月間「読む」単元が続くというケースも少なくありません。これでは、せっかく身についた書く力が定着しにくくなってしまいます。
「作家の時間」では、毎週必ず1時間、継続的に書く時間を確保します。これにより、量をこなすことができ、書くことに慣れ、自然と力が伸びていきます。最初は短くて拙い文章でも、毎週書き続けることで、徐々に文字数が増え、表現も豊かになっていきます。質はもちろん大切ですが、まずは量を確保することが、書く力を伸ばす上で非常に効果的です。
3. 自己肯定感が高まり、自信につながる
作家の時間では、自分の興味関心を深く掘り下げて書くため、他の子とは違う独自の視点や表現が生まれます。それを発表して友達に褒められたり、感想をもらったりすることで、「自分だけの作品」を創り上げたという達成感と、自己肯定感が高まります。
先日、ある子が「1週間の命」という題で途中まで書いた物語を発表してくれました。すると、他の子から「物語の設定が面白い!」「続きが気になる!」といった感想が次々に寄せられました。自分の好きなことを自分の言葉で表現し、それが誰かに伝わる喜びは、子どもたちの自信に大きくつながります。
子どもを支援する上で気をつけたいこと:まずは「書く」ことを楽しませよう
子どもたちの「書く力」を伸ばすために、私たちが支援する上で特に気をつけていることがいくつかあります。それは、「とにかくまず、書くことを楽しむこと」です。
たとえば、子どもが書いた文章に対して、最初から以下のような細かい指摘はしません。
- 「この漢字が間違っているよ」
- 「ここの構成が少しおかしいかな」
- 「句読点の使い方が違うね」
このような細かい修正から入ってしまうと、子どもは「また直される…」と萎縮してしまい、書くことへの意欲が失われてしまう可能性があるからです。まずは、子どもが自由に、楽しく書くことを何よりも優先します。これにより、書くことへの意欲を育て、文章を書き続ける土台を作ることが大切だと考えています。
2. 書いたものを「共有」する場を大切に
書く力を伸ばす上で大切なのは、書いたものを誰かに読んでもらう、という体験です。作家の時間では、自分の作品を友達に読んでもらったり、クラス全員の前で発表したりする時間を必ず設けています。
「すごい発想だね!」「ここを読んで感動したよ!」
そういった素直な感想が飛び交うことで、子どもたちは達成感を得て、さらに「書いてみよう」という意欲が湧いてきます。書くことは、誰かに伝えること。その喜びを知ることで、子どもたちの表現力はぐっと伸びていくのです。ご家庭でも、お父さんやお母さんが熱心な読者になることが、お子さんの意欲を引き出す一番の方法です。
3. 題材や構成で悩んだら、コーチングで支援する
「何を書けばいいかわからない…」「どうやって書けばいいんだろう」と悩む子どももいます。そんな時こそ教師の出番、ご家庭では保護者の出番です。すぐに答えを教えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いかけてみてください。コーチングの手法で対話をすることで、お子さんは自分で考え、答えを見つける力が身につきます。これは、学校の学習だけでなく、社会に出てからも役立つ重要なスキルです。
AIの効果的な使い方:新しい「読者」や「コーチ」としての活用法
AIツールを、書く際のサポートに活用するのも一つの手です。
たとえば、子どもが書いた文章をAIに入力すると、「読者」としてポジティブなフィードバックを返してくれます。「この部分、面白かったよ」といった感想を返してくれることで、子どもは書くことへの自信を深めることができます。
さらに、「良いコーチになってください」といったプロンプト(指示)を入れることで、AIが「コーチ」となり、子どもとの対話を通して、どうすれば文章がより良くなるかを一緒に考えてくれる、といった使い方も可能です。題材を考える手助けをしてもらったり、書いた文章をより良い表現に推敲してもらったりと、使い方は多岐にわたります。
ただし、注意も必要です。AIに文章を全て書かせてしまうと、書く力は伸びません。教師は、子どもたちのAIの使い方を常に把握し、コントロールするようにしています。ご家庭でも、保護者の方が、お子さんのAIの使い方を一緒に確認したり、使い方について話し合ったりして、あくまで「書く力を伸ばすためのツール」として活用することが大切です。AIの進化は早く、今後も様々な活用法が出てくるでしょう。お子さんと一緒に、新しいツールの使い方を模索していく姿勢も大切です。
家庭でできる「作家の時間」の取り組み
では、ご家庭ではどのように「書く力」を伸ばしていけば良いのでしょうか。
1. ポジティブなフィードバックを心がける
お子さんが書いたものを読んだら、まずは良い点を具体的に褒めてあげましょう。「この表現、素敵だね」「ここ、面白かったよ」といったポジティブな言葉をかけることで、お子さんは「自分の文章を読んでもらえた」「認めてもらえた」という喜びを感じ、次の作品への意欲につながります。
2. アウトプットの場を設ける
学校のようにたくさんの人に読んでもらうことは難しくても、以下のような形でアウトプットの場を設けることができます。
- 家族に読んでもらう: 書いたものを家族に発表したり、感想を伝えあったりする。
- コンクールに出展する: 作文コンクールなどに挑戦してみる。
- AIに読んでもらう: AIに作品を読ませて、感想やアドバイスをもらう。
3. 日常生活で「書く」機会を増やす
日記、手紙、おつかいのメモなど、日常生活の中に「書く」機会を自然に取り入れていくことも効果的です。例えば、家族旅行の計画を立てる際、お子さんに「旅のしおり」を作成してもらったり、祖父母に手紙を書くことを勧めてみたりするのも良いでしょう。
4. 親子で一緒に「作家の時間」を実践してみる
お子さんだけが書くのではなく、親子で同じテーマについて書いてみるのも良いでしょう。例えば、「今日の夕食で一番美味しかったもの」というテーマで、各自が文章を書いてみてください。お互いの視点の違いを知ることができ、新しい発見があるかもしれません。
おわりに
子どもたちが書く文章には、その時々の感性や、子どもにしか思いつかない素晴らしい発想が詰まっています。
つい「誤字脱字がないか」「論理的に書けているか」といった細かい部分に目が行きがちですが、まずは「書くことって楽しい!」という気持ちを大切に、お子さんの作品を温かく見守ってあげてください。
作家の時間を通して、書くことの楽しさを知り、自分の言葉で表現する喜びを感じた子どもたちは、きっと自分らしい豊かな文章を紡ぎ出すことができるはずです。
作家の時間の学校での実践についてはこちら↓
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント

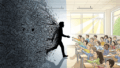

コメント