HIROです。90年代初めに大学を卒業後、新卒で日本の銀行に就職し、外資系の金融機関を経て、通信教育で教員免許をとり、今は小学校の教師をしています。Xでも情報発信をしているので覗いてみてください。HIRO(@fuchan_teacher)
このブログでは子どもたちの国語力向上のための家庭学習でのヒントをお伝えしていきます。これまでのビジネス経験や小学校教員としての実践をもとにした、子どもたちが楽しく国語力を上げるための方法をご紹介しますので、「これはできそうだな。」というものがありましたらぜひ参考にしていただければと思います。
80年代バブル景気の頃に地方の公立高校を卒業して上京し、早稲田大学商学部に入学しました。大学時代はアイスホッケーを中心とした生活を送る一方、演劇サークルにも所属、休み期間中はふらっと海外へ一人旅に行くという生活をしていました。
学生時代は教育に全く関心がなかったのですが、自分の子育て経験を通して教育の仕事の素晴らしさに目覚め、通信教育で小学校教諭と特別支援学校教諭の免許を取得し、採用試験を受けて41才のときに教育の世界に飛び込みました。その前は日系や外資系の金融機関で働いていました。自身のビジネス経験を通して情報活用能力や論理的思考力、批判的思考力の土台となる国語力の大切さを感じてきました。教員になってからは、国語力向上を自身の研究テーマとして実践を重ねています。
なぜ民間企業をやめて41才で教師になったのか?
民間企業を辞めて40才を過ぎて教師になったので「なぜ先生になったんですか?」とよく聞かれます。実は教師というのは学生の頃からなりたくない職業の1つでした。中学生や高校生のときは校内暴力が当たり前で、教室に竹刀を常備する先生もいました。先生に「歯を食いしばれ!」といってグーで殴られるなど日常茶飯事、そんな時代だったので教師は正直嫌いでした。
ただ小学校時代はとても良い思い出として残っていて、週末に先生と一緒に山登りやサイクリングに行くような牧歌的な小学校時代を過ごしました。担任の先生はガリ版でクラスの作文集を作ってくれるような方でした。今教師をやっていること、そして国語力向上を自分のテーマにしているのは、その先生の影響もあると思います。
海外への憧れと海外赴任
野球が好きで少年野球のキャプテンなどをするような活動的な子どもでしたが、一方で「なぜ人は存在しているのか」「真理って何」というようなことを考えてしまう、ちょっと変わった子どもだったと思います。小学校のときから読書が好きで、ジャンル問わず乱読していた記憶があります。中でも「ドリトル先生シリーズ」が好きで繰り返し読んでいました。本の影響でいつか自分も海外に出て、いろいろな世界を見てみたいと夢見ていました。
大学時代の就職活動では「うちの銀行ならすぐに海外赴任できるよ。」という声につられて日本の銀行に就職しました。その声は嘘ではなく、25才で香港に赴任しました。ちょうどイギリスから中国に返還される時期で貴重な経験をすることができました。ディーリングルームの隔離された部屋の中で、現地スタッフ4人と日本人自分1人という状況でしたが、拙い英語で必死にコミュニケーションをとっていました。香港勤務前はTOEIC660点くらいの英語のレベルで、今思えばよく海外赴任をさせてくれたなと思います。
激動の金融危機を乗り越える
当時の日本の金融機関を取り巻く環境は不良債権問題からの金融危機で激動の時代でした。その中で香港支店の資金調達の責任者を任されていたのですが、当時勤務していた銀行も外貨の資金調達が困難な状況でした。そこへさらにアジア通貨危機という金融環境の変化も重なり、なかなかの修羅場を乗り越えた経験となりました。英語力も帰国時にはTOEIC820点レベルになっていました(令和6年受験時945点)。帰国から1年後イギリスの銀行へ転職しました。30歳で初めての転職、子どもが生まれたばかりの時期で今後に不安を覚えながら過ごしていたのを覚えています。転職先では新しいビジネスを立ち上げるプロジェクトチームの一員として仕事をしました。ゼロからビジネスを立ち上げ、それを大きくしていくという体験をすることができ、仕事の面白さに目覚めた時期でした。今でもプロジェクトベースの学びを大事にしているのはこの時の経験がもとになっているのだと思います。
シンガポール研修での悔しさ
ここでの経験で最も印象に残っているのは、シンガポールでのマネジメント研修です。世界各国から集まった50人ほどのマネージャーたちと10日間、グループで課題を解決する研修がありました。グループでのワークショップが中心の研修でしたが、当時の私の英語力では課題解決のためのグループでの話し合いに入れず、食事時間の会話もついていけず、とにかく苦しい10日間でした。グループでは各国から来た同僚がいましたが、だんだんと私以外でグループワークを進めていく雰囲気が・・。このときの悔しい経験は小学校教師になってからも、子ども理解の上でとても役立っていると感じています。子どもの国語力を伸ばしたい、という思いはこの時の体験ももとになっていると思います。
アメリカ同時多発テロ事件
教師になろうと思ったきっかけの1つとして、2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ事件があります。香港勤務時代の大切な友人達がこの事件の犠牲になりました。転職する際に送別会を開いてくれて、「お前ならどこでもやっていけるよ」と励ましてくれた友人達でした。その言葉は、当時の私にとって大きな支えとなり、小学校教師を志した際にも、私の背中を押してくれた大切な言葉です。大切な友人を失いしばらく精神的にも落ち込む時期が続きました。その時に考えたことは「友人たちの分まで、ちゃんと生きなければならない」という思いでした。この事件からすぐに小学校の教師になろうと思ったわけではありませんが、自分の生き方を定期的に問い直すきっかけとなりました。
幼稚園の園長先生との出会い
「なぜ教師になったのか」という理由のもう一つに、自分自身の子育て経験があります。特に、子どもが通っていた幼稚園の園長先生との出会いは、教育という仕事の素晴らしさに気付いた大きなきっかけでした。園長先生は、学生時代から貯めたお金で少しずつ土地を買い、手作りの幼稚園を創り上げた方でした。私の子どもたちも、そんな園長先生の幼稚園の森でのびのびと育っていきました。
園長先生は毎朝、暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、膝をついて笑顔で園児たちを迎えていました。幼稚園には柿やびわなど様々な実がなる木が植わっていて、庭にはヤギやチャボがいました。園児たちは季節の移り変わりを五感いっぱいに感じながら過ごしていました。生活から感じ取ったことを劇にしたり、歌にしたりして学びに繋げていました。特に園児たちの歌を聴くと、上手いとか下手だとかを超越した力を感じて感動しました。「教育の仕事ってすごい」と心の底から思ったのは、このときだったと思います。
今自分が、子どもたちが活動しながら学ぶ授業スタイルを追究しているのも、このときの生活に根差した園長先生の教育の影響を大きく受けていると思います。子どもたちがいきいきと過ごす学びの場を、いつか自分自身の手で作ってみたい。その思いは、今でも持ち続けています。
2度目の転職と通信教育開始
2回目の転職は米系の不動産金融会社です。当時の不動産業界はプチバブルの様相を呈しており、イケイケどんどんの状況でビジネスが拡大していく中、アジア地域の財務責任者として採用され、日本を含むアジア各国の資金調達と金利や為替リスク管理を担当しました。米ドルの資金調達のため米国本社とやりとりし、日本の銀行と円資金調達の交渉をし、フィリピンペソの資金調達があれば現地に赴いて現地の銀行と交渉し、英文契約書の交渉をして資金調達の事務スキームを作る、といった感じの仕事でした。新規案件ごとに営業、審査、税務、法務、会計、財務と各部署からのプロフェッショナルが集結してプロジェクトを進めていくのがとても楽しく、プロジェクトベースの学びを作ることを大事にしている今に繋がっています。転職して数年後、金融業界を揺るがせたサブプライムローン問題が起こりました。新規案件は凍結、財務担当者として資金調達に奔走した日々でした。その中で今後の身の処し方についても考えるようになり、その中で教育の仕事に携わりたいと強く思うようになりました。
まずは通信制の大学で小学校の教員免許を取得することにしました。仕事をしながら定期的にレポートを提出し、スクーリングに参加するのは大変でしたが、もう一度大学に入って学びなおすという経験はとても楽しいものでした。1か月間の教育実習が大きなハードルで、それほど長い期間仕事の休暇をとるのは難しい状況でしたが、当時の上司や同僚の理解もあり、無事実習に参加することができました。
教育実習と採用試験
教育実習をさせて頂いたのは小学校4年生のクラスでした。実習最後の日にはクラスの子どもたちが泣いて別れを告げてくれました。子どもたちとの関わりを通して心が動く瞬間が多々あるのが、教師の仕事のやりがいの1つでもあります。その後、特別支援教育の免許も取得し教員採用試験に挑みました。当時はピアノや体育の実技試験もあり、仕事をしながらの採用試験準備は大変でしたが、無事に合格することができました。
以上が「なぜ教師になったの?」に対する答えとなります。小学校の先生になるという決断は正直簡単なものではなく、いざ先生として仕事を始めてみると、その大変さは予想をはるかに上回るものでした。しかし子どもたちの成長を近くで支え、見守るこの仕事にとてもやりがいを感じています。
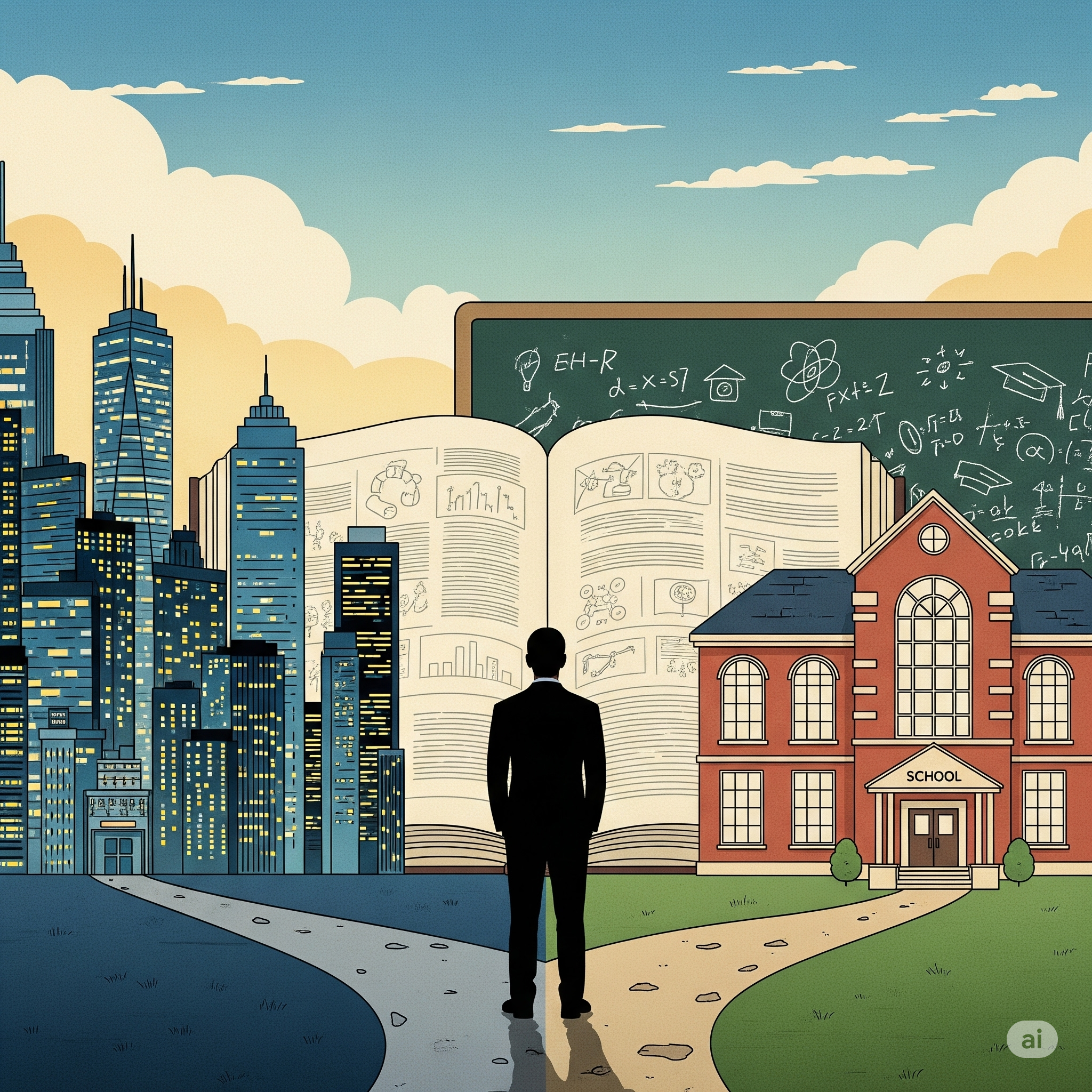
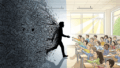
コメント