いつもお読みいただき、ありがとうございます。このブログでは、ご家庭で日々お子さんの教育と向き合っていらっしゃる保護者の方に、少しでもお役に立てる情報を発信したいと思っています。
これまでのブログで、子どもたちが文章を書くためのモチベーションをいかに高めるか、そして論理的な文章を組み立てるための「型」についてお話ししてきました。しかし、文章は「書きっぱなし」では終わりません。今回は、書いた文章をもう一度見直し、より良いものに磨き上げるための「推敲(すいこう)」と「校正(こうせい)」、そしてその意欲を生み出す「共有」というプロセスについて、私の実践を交えながら深く掘り下げていきたいと思います。
推敲・校正はなぜ難しいのか
文章を書き終えた後、子どもたちに「自分で読み直してみよう」「もっと伝わるように工夫してみよう」と促しても、実はこの作業は非常に難しいものです。なぜなら、推敲は単に誤字脱字を直すだけでなく、より適切な言葉を選んだり、表現を工夫したり、文章の構成を練り直したりする作業だからです。これには、「書く力」だけではなく、多様な文章を読み、表現の引き出しを増やす「読む力」も総合的に必要となります。
「推敲」とは、文章の内容や表現をより洗練させることです。一方、「校正」とは、誤字・脱字や文法的な間違い、句読点の抜けなどを修正し、文章を整える作業です。この二つをセットで指導するようにしていますが、どちらも決して簡単な作業ではありません。
【教師の苦労と子どもの学びの壁】
特に、自分の書いた文章を客観的に読み直すことは、子どもにとって非常に困難です。自分の意図や思考が文章に反映されているか、読み手に誤解なく伝わるか、といった視点を持つには、かなりの訓練が必要です。学校の授業では、教師が一人ひとりの文章を丁寧に見て、赤ペンを入れて直していくことが多いのですが、これを35人以上のクラス全員に行うのは大変な労力です。そして、苦労して直しても、子どもたちがその意図を十分に理解し、次の文章に活かしてくれるとは限りません。正直なところ、直したはいいものの、子どもが「直してくれない」「読んでくれていない」といった様子を見ると、教師としては悲しい気持ちになることもあります。
現代のツール「AI」を賢く活用する
正直なところ、文章の校正、特に誤字脱字や句読点の修正といった部分は、今後の教育においてICT機器やAIの助けを借りるのが効率的だと感じています。もちろん、小学校の段階でAIに全てを任せてしまうと、子どもたちの文章力の向上には繋がりません。重要なのは、「AIをどう使うか」という視点です。
私は、AIは「すべてをやってくれる道具」ではなく、あくまで「ヒントを与えてくれるパートナー」として活用すべきだと考えています。
【AIの具体的な活用法】
- 校正の補助としてAIを活用する 子どもが書いた文章をデジタル入力(PCやiPadのタイピング)させて、それをAIに読み込ませます。そして、保護者の方がプロンプトを工夫し、「誤字脱字や句読点の修正が必要な箇所を赤で直してください」と指示すれば、一瞬にして完璧な校正案が提示されます。この手間を補助してもらうことで、子どもたちはより重要な「推敲」に時間を割くことができます。
- 推敲の提案をAIにさせる 文章の内容や表現を磨き上げる推敲は、AIに「直させる」のではなく、「提案させる」のが良いでしょう。 例えば、
- 「この文章をより説得力のある表現にするにはどうすればいい?」「この『〜と思った』という表現の代わりに使える、別の言葉をいくつか提案してください」「この段落に、読者の注意を引くような書き出しを提案してください」
推敲・校正を支える「目的意識」
しかし、どれだけ優れたツールを使っても、子どもに「より良い文章を書きたい」という内発的なモチベーションがなければ、ただの機械的な作業になってしまいます。推敲・校正は、より分かりやすく、より説得力のある文章を書きたいという強い思いがあってこそ、本気で取り組めるものです。
その「もっと伝えたい!」という目的意識やモチベーションを育むために、最も大切なのが「共有」というプロセスです。書いた文章を誰かに読んでもらい、それに対する反応を得るというアウトプットの場があることで、子どもたちは「書いて終わり」ではない、文章の本当の価値を知ることができます。
共有が子どもを動かす
子どもたちは、自分の書いた文章が誰かに読んでもらえることを心から喜びます。「書いてアウトプットする」だけでなく、そのアウトプットした文章を「誰に読んでもらうか」という意識が、推敲や校正への意欲を大きく左右します。
【多様な共有の方法】
- クラス全体での発表 自分の書いた文章をもとに3分間スピーチをしたり、全体の前で読み上げたりする場を設けます。友達が真剣に自分の話を聞いてくれる姿を見ることは、子どもたちにとって大きな自信となります。この発表の場は、書く活動だけでなく、自分の考えを簡潔にまとめて話す「話す力」も養います。
- グループやペアでの読み合い グループやペアで文章を交換し、読み合う時間を設けます。人前で発表するのが苦手な子でも、身近な友達とであれば安心して自分の作品を共有できます。ペアをどんどん変えて様々な人に読んでもらうことも、多様な視点を得る上で有効です。
- ICT機器の活用 タブレットなどのICT機器を使えば、自分の作品をクラス全体に瞬時に共有することができます。全員の作品が読める環境を整えることで、子どもたちは互いに刺激を受け合い、「自分ももっと頑張ろう」という気持ちになります。また、作文コンクールなど対外的な場に応募することも、一つの大きなモチベーションになります。入選するかどうかだけでなく、「社会に向けて自分の文章を発信する」という経験そのものが、子どもたちの意欲を高めるのです。
「ポジティブ」と「建設的」なフィードバック
共有の場で大切なのは、フィードバックの質です。単に「よかったね」と褒めるだけでなく、今後の成長につながる「建設的なアドバイス」をもらうことも重要です。
- ポジティブなフィードバック 「〇〇さんの文章、すごく分かりやすかったよ」「この表現、面白いね」といったポジティブな言葉は、子どもが「書いてよかった!」と感じる大きな喜びとなります。自分が一生懸命書いた文章が誰かに読まれ、理解してもらえたという経験が、次の創作へのエネルギーになります。
- 建設的なアドバイス 「この部分をもう少し詳しく書いたら、もっと面白くなると思うよ」「この段落を入れ替えたら、もっと分かりやすくなるんじゃないかな」といった、成長を促す具体的なアドバイスも不可欠です。
この二つのフィードバックをバランスよく与え、受け取ることで、子どもたちは「書く」という表現活動と、その活動に対する他者からの反応がセットであることを学びます。そして、この学びが、次の活動への意欲へとつながるのです。
書くことの本当の楽しさ
推敲や校正は、決して楽な作業ではありません。しかし、それは「より相手に伝えたい」という強い目的意識があるからこそ、真剣に取り組めるものです。私は、子どもたちに、文章を書くことは単に言葉を並べることではなく、「誰かに何かを伝える」というコミュニケーション活動であることを伝えています。
日本の学校教育では、学習指導要領の資質能力が「話す・聞く」「読む」「書く」の三つの領域に分かれていることから、教科書もそれぞれの単元が独立して構成されている傾向にあります。しかし、現実の社会では、これらの力は密接に結びついています。今回の「推敲・校正」と「共有」のプロセスは、まさにその統合された力を育むための実践です。
今回お話しした「共有」と「フィードバック」の場は、そのコミュニケーションの楽しさを子どもたちに体感させるためのものです。文章を書くことを、単なる学校の課題ではなく、自分の思いを社会に発信し、誰かと繋がる喜びを感じる機会にしていくことが、子どもたちの生涯にわたる「書く力」を育む上で最も大切なことだと私は信じています。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑥~説明文を書くための対話の時間編 – 家庭学習のヒント

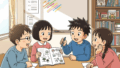
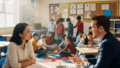
コメント