いつもお読みいただき、ありがとうございます。このブログでは、ご家庭で日々お子さんの教育と向き合っていらっしゃる保護者の方に、少しでもお役に立てる情報を発信したいと思っています。
前回のブログでは、説明文の文章構成について、子どもたちに指導している「序論・本論・結論」という基本的な型や、「頭括文・尾括文・双括文」といった応用的な型をお伝えしました。しかし、ただ単に構成を伝えて「さあ、書いてみましょう」と言っても、子どもたちは正直、書く意欲が湧いてきません。これは私たち大人でも同じではないでしょうか。何かしらのモチベーションがないと、いくら素晴らしい「型」を教えられても、本気で書こうとは思えないものです。
文章を書く上では、物語を書くことと説明文を書くことには大きな違いがあると、私は考えています。物語はそれ自体がクリエイティブな活動であり、自分の頭の中にある発想や表現を、誰かに伝えたいという本能的な欲求に結びつきやすいものです。だから、多くの子供たちは物語を書くことを楽しみます。しかし、説明文となると、「なんでこんなこと書かなきゃいけないの?」と苦痛に感じてしまう子が少なくありません。
読む側も同じです。興味のない内容の説明文を読まされるのは、大人でも苦痛ですよね。説明文は、読むにしても書くにしても、「なぜそれをするのか」という目的意識、つまり「モチベーション」が、取り組みへの意欲を大きく左右するのです。
今回は、この説明文を書く「作家の時間」を、いかにして楽しく、モチベーション高く取り組ませるか、そのために私が実践している「対話の時間」について詳しくお話ししたいと思います。
書く「必然性」を生み出す「対話の時間」
子どもたちが説明文を書く上で最も大切なのは、書くことへの「必然性」や「必要感」を生み出すことです。つまり、「なぜこの文章を書く必要があるのか」という理由を、子ども自身が感じることが大切です。
そのために私が設定しているのが、ディベート(討論)形式を取り入れた「対話の時間」です。
【対話のテーマは子どもたちが決める】
対話のテーマは、私が一方的に決めるのではなく、子どもたち自身から募るようにしています。彼らが心から興味を持っているテーマでなければ、深い対話は生まれないからです。
- 「家で飼うなら、犬と猫どっちがいい?」
- 「きのこの山とたけのこの里、どっちが好き?」
- 「夏休みに行くなら、海と山どっちがいい?」
このような、身近で、かつ意見が分かれそうなテーマを子どもたちが選ぶと、様々な意見が飛び出してきます。彼らが決めたテーマであれば、自ずと意欲も高まります。
3つの討論形式を使い分ける
対話の時間は、クラスの人数や目的に合わせて、以下の3つの形式を使い分けています。それぞれにメリット・デメリットがあり、これらをミックスして使うことで、より効果的な学びを促すことができます。
- クラス全体での討論
- グループでの討論
- ペアでの討論(マイクロディベート)
1. クラス全体での討論:様々な意見に触れる
メリット: 最大のメリットは、多様な考えに触れられることです。まだ自分の意見が固まっていない子どもでも、クラスの様々な意見を聞くことで、「なるほど、そういう考え方もあるのか」と視野が広がり、自分の意見を形成する上で役立ちます。特に、自分の根拠がまだ弱いと感じている子にとっては、他の子の意見を参考に、自分の主張を補強する大きなチャンスとなります。
デメリット: クラスの人数が多い場合(30人以上)、全員が発言する機会を確保するのが難しいことです。発言しないまま時間が終わってしまう子も出てくる可能性があります。もちろん、話を聞いているだけでも頭の中では考えているはずですが、やはり積極的に発言する機会は確保したいものです。
2. グループでの討論:協力して思考を深める
メリット: グループ討論は、参加する頻度が全体討論よりも格段に高まります。3人程度の少人数で役割分担をしながら進めることで、チームで一つの主張を組み立てる力が育まれます。相手の反論を予測し、どう切り返すか相談したり、「このデータを使おう」と協力したりする中で、協調性やコミュニケーション能力も養われます。
デメリット: グループで意見をまとめるため、個人の考えがグループの意見に引きずられてしまう可能性があります。本当は言いたかったことでも、グループの方向性に合わないため、我慢してしまうこともあるかもしれません。
3. ペアでの討論(マイクロディベート):思考のアウトプット力を高める
メリット: ペア討論は、最も個人の思考が深まる形式です。自分の意見を必ずアウトプットしなければならないため、主体的な取り組みが不可欠となります。相手の意見をしっかりと聞き、それに対して瞬時に考え、自分の言葉で反論する、という一連のプロセスを繰り返すことで、思考の瞬発力や論理的な構成力が鍛えられます。
デメリット: 自分の考えをしっかり持っていないと、討論が成立しにくいという点です。そのため、いきなりペア討論を行うのではなく、全体やグループでの討論を経て、ある程度考えがまとまった段階で導入するのが効果的です。
段階的な「書く」活動へ
私の実践では、これらの討論形式を以下のように組み合わせながら、子どもたちの「書く」モチベーションを高めています。
- 全体討論: まずはクラス全体で、各自がどちらの立場に立つかを決め、簡単な意見交換を行います。この段階で、様々な意見に触れ、自分の考えの土台を固めます。
- グループ討論: 次に、同じ立場の仲間とグループを組み、より深く議論します。相手の反論をどう切り返すかなど、論理的に考え、主張を強化する訓練をします。
- 執筆: ここで満を持して、論説文を実際に書かせます。これまでの対話で十分に思考を深めているため、子どもたちは「なぜ書くのか」という目的意識を明確に持っています。
この時、私は「きのこの山が好きだからきのこの山が良い」という単純な文章ではなく、以下のような構成で書かせるように指導します。
- 序論: 自分の立場(例:きのこの山が良い)をはっきり述べる。
- 本論: その根拠を2つ以上挙げる。
- 反論の反論: あえて、反対意見(例:たけのこの里の方が良い)を予想し、その反論を論破する。
- 結論: 序論で述べた結論をもう一度繰り返す。
思考を深める「立場を入れ替える」実践
さらに、私は、「本当はきのこの山が好きな子に、あえてたけのこの里の良さを書かせる」という実践も取り入れています。
これは、自分の立場に固執するのではなく、相手の立場に立って物事を考える力を養う上で非常に重要です。
- 「なぜ相手はそう考えるんだろう?」
- 「相手の主張の強いところはどこだろう?」
- 「どうすれば相手の論を崩せるだろう?」
このように、相手の視点に立つことで、自分の意見の弱い部分が見えてきます。そして、その弱い部分をどう補強すればよいか、という思考が働き、結果的に自分の主張をより強固なものにすることができます。
書くことは、話す・聞く・考えること
日本の学校教育では、学習指導要領の資質能力が「話す・聞く」「読む」「書く」の三つの領域に分かれていることから、教科書もそれぞれの単元が独立して構成されている傾向にあります。例えば、ある説明文を「読み」、次に「その文章を真似て書きましょう」という構成はよく見られます。
しかし、この方法では、読む文章に興味がなければ、当然その後の「書く」モチベーションは生まれません。
今回お話しした「対話の時間」は、この「話す・聞く」「読む」「書く」を統合させる試みです。
- 聞く:友達の意見を真剣に聞く。
- 話す:自分の考えを明確に話す。
- 考える:相手の意見を聞き、自分の考えを深める。
- 書く:対話で固まった自分の考えを、論理的に文章にする。
このように、書くことの前に「対話」という目的を設けることで、子どもたちはなぜ文章を書く必要があるのかを心から理解し、書くことへの意欲を自然に高めることができるのです。
この文章構成や論理的思考の力は、将来、様々な場面で役立ちます。例えば英検のライティング試験では、与えられたテーマについて英語で自分の意見を述べることが求められます。その構成は、日本語の説明文と全く同じです。自分の主張を述べ、その根拠を2つ挙げ、最後に結論を述べるというシンプルな型は、英語でも全く同じように通用します。
次回のブログでは、文章を書き終えた後の、より難しいけれど、最も重要なパートである「推敲(すいこう)」と、そして書いた文章を他者と「共有」することの重要性について、詳しくお伝えしたいと思います。本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑥~説明文を書くための対話の時間編 – 家庭学習のヒント
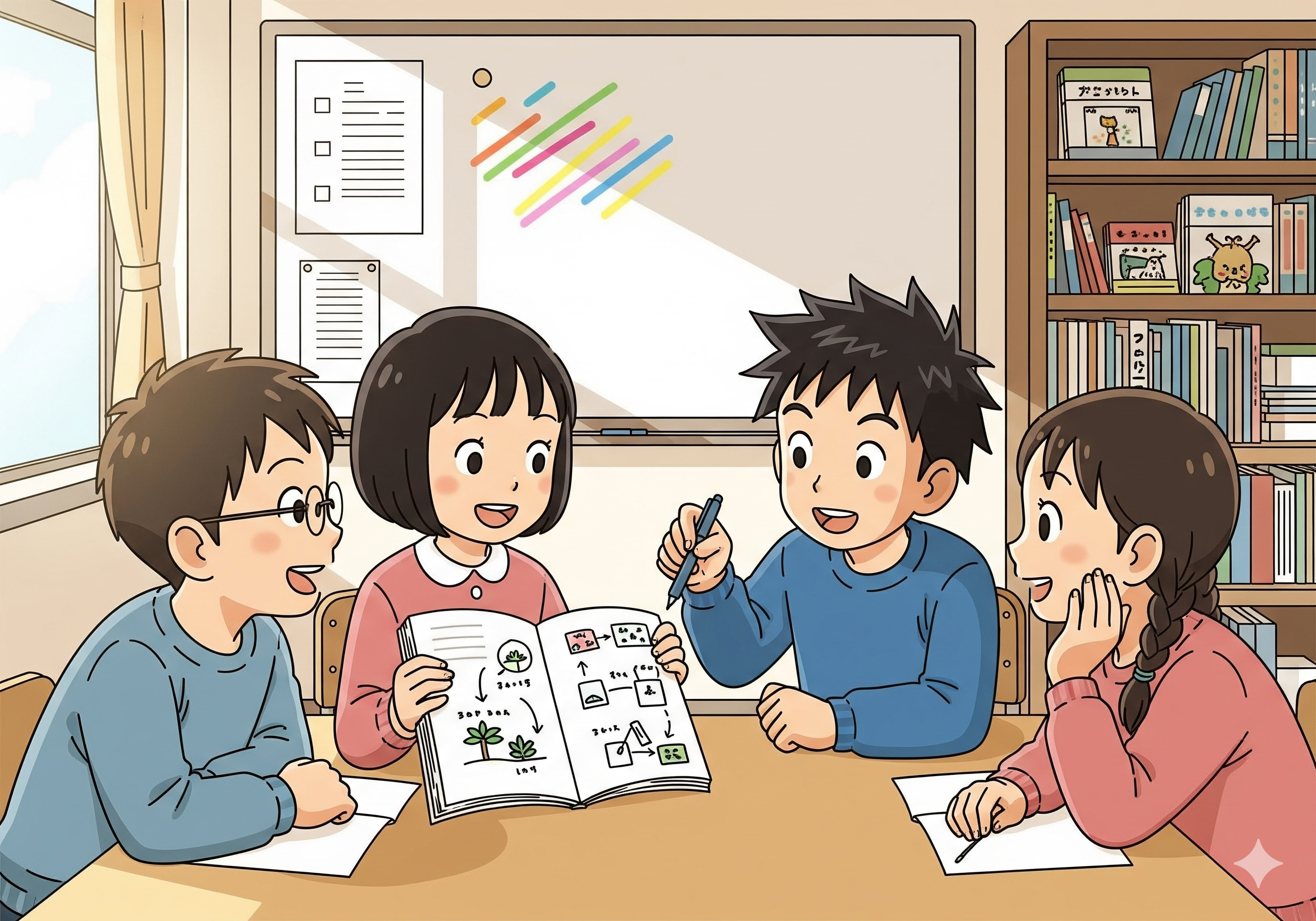


コメント