いつもお読みいただき、ありがとうございます。このブログでは、ご家庭で日々お子さんの教育と向き合っていらっしゃる保護者の方に、少しでもお役に立てる情報を発信したいと思っています。
前回は、子どもたちが「書くって楽しい!」と感じるための「作家の時間」の立ち上げについてお伝えしました。
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
今日はその続きとして、子どもたちが物語を書き始めるまでの導入、そして書き進める上での様々な工夫について、私のクラスでの実践を交えながら詳しくお伝えしていきたいと思います。
「うちの子、なかなか文章を書きたがらないのよね」 「どうすれば子どもの書く意欲を引き出せるのかしら」
そう感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。このブログでは、小学校の授業実践を参考に、ご家庭でも応用できるヒントをたくさんご紹介します。
子どもの「書きたい!」を自然に引き出す導入の秘訣
小学校の国語の授業で子どもたちが物語を書く活動は、彼らの想像力や表現力を育む上で非常に重要です。しかし、「さあ、物語を書きましょう!」といきなり言っても、子どもたちは戸惑ってしまうことが多いものです。どうすれば、子どもたちが自ら「書きたい!」と感じ、主体的に物語を創造する活動に入っていけるのでしょうか。
私のクラスでは、その導入に非常に時間をかけ、子どもたちの内発的な動機付けを促すことを何よりも大切にしています。
1. 前回の「楽しい」記憶を呼び起こすストーリーテリング
授業を始めるにあたって、まず前回の「作家の時間」(友達がドアから入ってきて20秒間動く様子を物語のように書くアクティビティ)で、子どもたちがどれだけ楽しそうに物語を創作し、互いの作品を読み合って盛り上がったかを思い出させるようにします。
「ねえ、覚えてる?前回の作家の時間、〇〇さんが書いた物語、すごく面白かったよね!みんなも『もっと書きたい!』って言ってたの、先生覚えてるよ。」
このように、先生が一方的に「書きましょう」と指示するのではなく、子どもたち自身が感じた「楽しかった」というポジティブな記憶を呼び起こし、そこから自然発生的に「物語を書きたい」という気持ちが生まれるように促すのです。
2. 「子どもからの声」を最大限に尊重する
ここで重要なのは、「〇〇さんが『書きたい』って言ってたけど、みんなはどう?」という問いかけです。先生が「物語を書いたらいいと思うんだけどどう?」と聞くのと、友達の「書きたい」という声を受けて「みんなもどう?」と聞くのとでは、子どもたちの反応は全く違います。
子どもたちの中から自発的に「うん、書きたい!」「いいね、やろう!」という声が上がるように仕向けることが、その後の活動のモチベーションを大きく左右します。先生が押し付けるのではなく、子どもたちが「自分たちで決めた」という感覚を持つことが、主体的な学びへと繋がるのです。
これはご家庭での学習にも応用できます。例えば、保護者の方が「これやってみたら?」と提案するよりも、「この前、〇〇ちゃんがこういう本読んでて面白そうだったけど、あなたも読んでみる?」とか、「このゲーム、ちょっとやってみたいんだけど、一緒にどうかな?」のように、あくまで選択肢の一つとして提示し、子ども自身が選択できるようにします。この自己選択こそが、学習が長く続くかどうかの大きな分かれ目となります。
3. あえて「壁」を作り、子どもの意欲を燃え上がらせる
子どもたちの「書きたい!」という声が高まってきたところで、私はあえて「壁」を作るようにしています。
「でもさ、みんな。物語を書くって言っても、いきなり書くのは難しいんじゃない?はっきり言ってかなり難しいでしょ?」
このように、少し意地悪な言い方をすることで(もちろん、クラスの実態に合わせて加減しますが)、子どもたちは「いやいや、先生!そんなことないよ!」「俺なら書けるよ!」と反発し、「できる自分」を見せようと意欲を燃え上がらせるのです。
さらに、「でも題材を考えるのも難しくない?」と畳みかけます。すると子どもたちからは、「題材なんていっぱいあるよ!」「この前やった冒険ごっこを物語にすればいいじゃん!」「僕、この間読んだ『転生したらスライムだった件』みたいな転生ものが書きたい!」「教科書に出てきた『森へ』の続きを書きたいな!」など、様々なアイデアが飛び出してきます。
このように、教師があえて「できない」という壁を設けることで、子どもたちは自分たちのアイデアや可能性を最大限に引き出そうと、前のめりになるのです。これは、子どもの主体性や創造性を刺激する上で非常に効果的なアプローチです。
アイデア出しと構成:物語を紡ぐための多様なアプローチ
題材が決まっても、いきなり書き始めるのは難しいものです。子どもたちが物語をスムーズに書き進められるよう、私はいくつかのアイデア出しと構成のヒントを提示しています。
1. 翻作(オリジナルを真似てアレンジ)のススメ
「何を書いたらいいか分からない」と悩む子どもたちには、「翻作(ほんさく)」という方法を提案します。「翻作」とは、既存の物語を少しだけ「変えて」自分なりのオリジナル作品にすることです。
- 登場人物を変える: 桃太郎の話で、桃から生まれたのが桃太郎ではなく、別の果物から生まれた誰かにする。
- ストーリーの一部を変える: 鬼ヶ島に退治に行った桃太郎たちが、鬼と仲良くなってしまう。
この方法のメリットは、元のストーリーを知っていることで、子どもたちが安心感を持って書き始めることができる点です。ゼロから全てを創造するのは大変ですが、ある程度の骨格があることで、楽しくアイデアを広げることができます。
2. 説明文にも目を向ける:多様な「書く」喜び
クラスには、物語を書くことに抵抗がある子もいます。「先生、僕、別に物語は書きたくないんだけど…」そんな声が上がった時、私は決して無理強いはしません。むしろ、「じゃあ、何だったら書きたいの?」と、子どもの主体的な興味を問いかけるようにしています。
すると、「動物が好きだから、動物について調べたことを書きたい!」「鉄道が好きだから、鉄道について書きたい!」など、説明文について書きたいという声も出てきます。
この時、私は徹底的に褒めます。「説明文、いいね!実はね、説明文って大きく分けて3つの種類があるんだけど知ってる?」と、ここでミニレッスンを始めます。
- 説明文(説明書タイプ): 動物の特徴、料理の手順、遊びのルールなど、何かを説明する文章。
- 紀行文: 旅の経験や風景を時系列で説明していく文章(私の海外旅行記もこれに当たりますね)。
- 論説文: 何かを主張し、その根拠を示す文章(小論文や論文のようなもの)。
このように説明文の多様性を提示することで、子どもたちは「物語」以外の「書く」選択肢があることを知り、自分の興味に合った題材を見つけやすくなります。中には「論説文に挑戦してみたい!」という意欲的な子も現れるので、選択肢の幅を広げることは非常に有効です。
構成の準備:物語の骨格を作る
題材が決まったら、次は物語の骨格である「構成」を考えるステップです。ここでも、子どもたちの特性に合わせていくつかの方法を提示します。
1. 付箋を使った「起承転結」
学校の授業でよくあるのが、物語の構成を考えるために付箋を使う方法です。
- まず、物語の「初め」「次」「その次」「終わり」といったように、起承転結の大きな流れを意識させます。
- それぞれの場面で「登場人物」「季節」「場所」「事件」「解決」といった要素を、付箋に書き出していきます。
- 付箋を並べ替えることで、物語の流れを視覚的に確認し、構成を練り直すことができます。
この方法は、物語の構成を論理的に理解し、全体の流れを把握する上で非常に有効な手立てです。
2. 自由な発想のマインドマップ
一方、より自由にアイデアを広げたい子どもたちには、マインドマップをおすすめします。
- 中央に物語のテーマ(例: 「冒険物語」)を書き、そこから思いつくままに連想される言葉やアイデアを枝分かれさせていきます。
- 「登場人物」「場所」「宝物」「敵」「助けてくれる人」「道具」「ハプニング」など、頭の中に浮かんだキーワードをどんどん書き出していきます。
- マインドマップが完成したら、そこから物語の要素を拾い出し、付箋の「起承転結」の構成に落とし込んでいく、という使い方もできます。
マインドマップは、発想を広げるのに優れており、構成を考えるのが苦手な子でも、アイデアを形にする助けになります。
3. 「とにかく書きたい!」子への対応
中には、頭の中にすでに物語の構成ができていて、「とにかく早く書き始めたい!」という衝動に駆られている子もいます。そのような子には、無理に構成を考えさせるのではなく、「いいね!じゃあ、どんどん書いてごらん!」と、その意欲を尊重して書かせます。
「書きながら考える」というタイプの子もいるので、彼らのスタイルを尊重し、自由に表現する機会を与えることが大切です。
執筆中のサポート:机間指導とカンファレンス
子どもたちが実際に書き始めたら、教師の役割は「一人ひとりに寄り添い、サポートすること」へと移行します。私は、机間指導(きかんしどう)とカンファレンスという形で、個々の子どもたちを支援します。
1. 集中して書く時間を確保する
まず、20分から30分程度のまとまった「書く時間」を確保します。日本の学校教育では、じっくりと文章を書く時間が不足しがちだと感じています。だからこそ、この「書く時間」を大切にし、教室が鉛筆の音だけが響く静かな空間になるよう促します。
2. カンファレンス(個別指導)で思考を深める
子どもたちが書き進める中で、「手が止まってしまった」「次が思いつかない」といった壁にぶつかることがあります。その時、教師が一人ひとりの机を回り、1〜2分程度で個別にアドバイスをします。これがカンファレンスです。
- 「今、どこまで書けたかな?」
- 「この登場人物は、今どんな気持ちだと思う?」
- 「次にどんなことが起こったら、読者はもっとワクワクするかな?」
- 「この表現、もっと良い言葉がないか一緒に考えてみようか」
このように、問いかけや共感を通じて、子どもたち自身が思考を深め、次に進むヒントを見つけられるようにサポートします。教師は「答え」を与えるのではなく、「考えるきっかけ」を提供する伴走者となるのです。
3. 手書きとタイピング、そして音声入力の選択
執筆方法については、以下の選択肢を提示しています。
- 手書き(鉛筆):
- 基本的には手書きを推奨しています。書く行為と思考が連動しやすいため、考えをまとめながら文章にするのに適しています。
- タイピング(PC):
- タイピングスピードが手書きの倍以上ある子には、PCでの入力も認めています。最終的にはタイピングスキルも上げていきたいと考えているため、積極的に活用させたい方法です。
- 音声入力:
- 字を書くのが苦手な子や、発達上の特性を持つ子には、補助的な手立てとして音声入力も認めています。ただし、音声入力だけでは段落や構成を意識するのが難しいため、入力後に自分で推敲・修正する作業が不可欠であることを伝えています。
音声入力は思考をアウトプットする速度は速いですが、文章の構造を意識しながら書くという点では、手書きやタイピングの方が優れていると感じています。音声入力はあくまで「手書きやタイピングの補助」であり、その後の思考整理と推敲にこそ価値があると考えています。
作品の共有とフィードバック:次なる意欲への架け橋
物語を書き終えたら、それで終わりではありません。20〜30分程度書き込んだ後には、必ず作品を共有し、互いにフィードバックし合う時間を設けています。この共有の時間が、子どもたちの「もっと書きたい」「次はもっと良くしたい」という次なるモチベーションに繋がる、非常に大切なステップです。
1. 全体共有で味わう達成感
クラス全体の前で、自分の書いた物語(途中まででも構いません)を読み上げる時間は、子どもたちにとって大きな達成感と喜びをもたらします。友達が真剣に自分の物語に耳を傾け、楽しんでいる姿を見ることで、「書いてよかった!」という気持ちが芽生え、さらなる創作意欲が湧いてくるのです。聞いている側の子どもたちも、「〇〇さんの表現、面白いな」「私もこんな風に書いてみたい」と刺激を受け、互いに高め合う関係が生まれます。
2. 多様な共有方法で安心感を確保
しかし、小学校高学年にもなると、人前で自分の作品を読むことに恥ずかしさを感じる子もいます。そのため、共有のやり方は、クラスの実態や子どもの性格に合わせて多様な方法を取り入れています。
- ペアでの読み合い: 友達同士で作品を交換し、お互いに読み合って感想を伝え合います。
- グループでの発表: 少人数のグループ内で作品を読み、意見を交換します。
- 教師とのカンファレンスで読み聞かせ: 全体の前で読むのが苦手な子には、教師との1対1のカンファレンスの中で、作品を読み聞かせてもらい、個別フィードバックを行います。
どのような形であれ、自分の作品が誰かに読まれ、それに対してポジティブなフィードバックを受け取る経験は、子どもたちにとって大きな自信とモチベーションに繋がります。
次回予告:物語を「より良くする」ためのポイント
今回のブログでは、子どもたちが物語を書き始めるまでの導入から、アイデア出し、構成、そして執筆中のサポート、共有のプロセスまでをお伝えしました。
次回は、子どもたちが書いた物語を「より良くする」ために、私が具体的にどのような指導ポイントを教えているのか、いくつかご紹介したいと思います。物語をさらに磨き上げ、読者に感動を与えるための具体的なテクニックについて、深掘りしていきます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑥~説明文を書くための対話の時間編 – 家庭学習のヒント


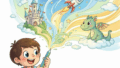
コメント