小学校の先生が実践する、子どもの心を育てる声かけのコツ
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。 今日は、少し専門的な内容から離れ、子どもの「心の力」を育むための声かけについて、お伝えしていきたいと思います。
私自身、小学校の教師として毎日30人以上の子どもたちと向き合っています。クラス全体を統率することももちろん大切ですが、一人ひとりの子どもたちと丁寧に向き合い、その子に合った声かけをすることが、何よりも重要だと感じています。
もちろん教師という仕事と、子育ては全く違います。仕事として子どもと向き合う際は、どこか客観的な視点を持つことができますが、自分の子どもとなると、どうしても感情が先立ち、冷静な対応が難しくなるものです。
このブログを読んでくださっているお父さん、お母さんの中には、「頭では褒めたほうがいいと分かっているけど、どうしても叱ってしまう」「褒めようと思っても、褒めるところが見つからない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。それは決して特別なことではありません。それは、それだけ真剣にお子さんと向き合っている証拠だと、私は自分の子育て経験を通して感じています。
今日の記事では、そうした前提を踏まえつつ、私が小学校の教師として、そして親として実践している、子どもへの声かけのポイントについてお話ししていきます。
1. 「叱る」と「褒める」のバランス
子育てにおいて、「褒める」と「叱る」は、どちらも欠かせない要素です。 「ダメなことはダメ」と教えなければ、子どもは社会のルールを学ぶことができません。しかし、叱ってばかりでは子どものやる気を奪い、自己肯定感を著しく下げてしまいます。
では、どのくらいのバランスが良いのでしょうか? 私は、「1つ叱ったら、5つ以上褒める」という意識を持つことが大切だと考えています。できれば1対10くらいでもいいかもしれません。 子どもは、大人が思っている以上に、叱られたことを強く記憶しています。だからこそ、その何倍も「あなたの良いところをちゃんと見ているよ」というメッセージを伝えることが重要です。
また、「叱る」ときには、感情的にならないことも大切です。 「あなたは本当にダメな子ね!」と人格を否定するような言葉や、「何回言ったら分かるの?」といった余計な一言は避けるべきです。代わりに、「アイメッセージ」を意識して伝えましょう。
- 「私(I)は、あなたが○○したとき、悲しい気持ちになったよ」
- 「私は、あなたが○○してくれると、とても嬉しいよ」
このように、主語を「あなた」ではなく「私」にすることで、子どもは「自分は否定された」と感じることなく、素直に話を受け止めることができます。
2. 「偉いね」ではなく「価値づけ」をする
特に、小学校中学年までは、良いところをどんどん褒めることが効果的です。しかし、思春期に入ると、「どうせ自分をコントロールするために褒めているんでしょ?」と、子どもはやや斜に構えた見方をすることもあります。
そのような時期になったら、単に「偉いね」と褒めるのではなく、「価値づけ」をする意識が重要です。
価値づけとは、「子どもの行動や存在の、良い点や重要性を具体的に言葉にして伝えること」です。
例えば、
- 「机に向かって座れたんだね。勉強に向かおうとしている、その気持ちが大事だと思うよ」
- 「作文のこの部分、登場人物の気持ちがすごく伝わってくる表現だね」
このように、具体的な行動や成果を言葉にして伝えることで、子どもは「自分のことをよく見てくれている」と感じ、自己肯定感を高めることができます。
3. 「プロセス」を褒め、良い点を伸ばす
人間は誰しも、完璧ではありません。欠点がない人などいないのです。 つい、子どものできていない部分、欠点ばかりに目がいってしまいがちですが、欠点を指摘して直させるよりも、良いところを徹底的に伸ばしてあげる方が、結果的にその子の持つ欠点を覆い隠してくれるものです。
例えば、少し行動が雑と言われる子がいたとします。その子の欠点を指摘するのではなく、その子が持つ「行動力」や「即断即決力」といった長所に目を向け、そこを徹底的に褒めて伸ばしてあげましょう。
良い点を見つけるのが難しいと感じる方は、「褒めるための仕組み作り」を意識的に行いましょう。 たとえば、
- 「おうちで作家の時間」:一緒に文章を書き、感想を伝え合う
- 「すごろく作り」:一緒にルールを考え、協力してボードを完成させる
- 「料理」:一緒に料理を作り、できた料理を一緒に食べる
こうした活動を通して、子どもは「結果」だけでなく、「プロセス」の中で様々な努力をしています。
- 「どういうテーマにしようか?」と一生懸命考えている姿
- 「どうしたらもっと面白くなるだろう?」と工夫する姿
- 「最後まで諦めずにやり遂げた」という姿勢
こうしたプロセスを親がしっかりと見取り、そこを「すごいね!」「その発想は素晴らしいね!」と具体的に価値づけてあげることが、子どもの自信と探究心を育みます。
まとめ:幸せに生きる子どものために、ありのままを受け入れる
高校野球の世界でも、勝利至上主義ではなく、プロセスを大切にするチームが結果を残しています。結果だけでなく、その過程でどれだけ楽しめたか、成長できたかを重視することは、子どもが幸せに生きるための礎となります。
子どもの「心の痛み」が分かる人間に育てるためにも、まずは親が子どもを信じ、ありのままを受けい入れる姿勢が大切です。
「大丈夫だよ」と、いつでも受け入れてもらえる場所がある。そう感じることで、子どもは安心して様々なことに挑戦できるのだと思います。
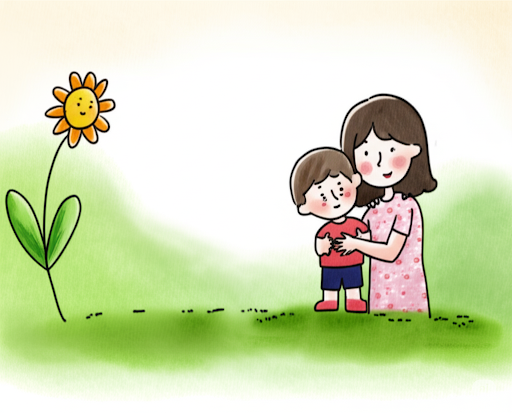


コメント