自己肯定感を上げるツール
近年、日本の教育界では”探究学習”や”対話的な学び”といった言葉が主流となり、”これからの時代は知識より思考力だ””ただひたすら反復練習を繰り返すドリル学習は時代遅れだ”といった意見を耳にする機会が増えました。確かに、変化の激しい現代において、与えられた知識をただ暗記するだけでは不十分かもしれません。 しかし、私はドリル学習だって大切だと思っています。基礎学力をつけるにはドリルによる反復は非常に効果的です。基礎学力は探究的な学びを進めたり、思考力を働かせたりする際の土台となるため、バランスを考えながら、楽しく取り組めるように工夫していければよいと考えています。
第1章:ドリル学習をする上で意識したいこと
ドリル学習をする上で、楽しく取り組めるような工夫をしていくとよいと思います。お勧めは時間を測るということです。繰り返し問題を解くことで解くスピードが速くなり、自己肯定感も生まれます。
- “できる!”という成功体験が自己肯定感を育む ドリル学習では、”自分はできる!”という成功体験を積み重ねることができます。同じ問題や、似たような問題を繰り返し解くことで、子どもは”最初は分からなかったけど、頑張ったら解けるようになった” “前よりも速く、正確にできるようになった”という自分の成長を”実感”することができます。 勉強の世界では、時に”難しい問題”にばかり挑戦し、”わからない” “できない”という状況に直面することがあります。しかし、ドリル学習では、”できた!”という達成感を何度も味わうことができます。この”頑張ればできるんだ”という感覚こそが、自己肯定感を育む上で最も重要な要素です。この成功体験が、”勉強って楽しいな””もっと頑張りたいな”という意欲に繋がり、学習のモチベーションを維持する原動力となります。
- 勉強の”ハードル”を飛び越える第一歩 子どもが”今日はなんだか勉強したくないな…”と感じる日でも、ドリル学習は有効です。勉強を始めることは、子どもにとって大きなハードルです。
“じゃあ、簡単な計算問題だけでもやってみようか” “漢字練習を5問だけやったら、もう終わりでいいよ”
このように、ドリル学習は”とにかく机に向かう”という、最も大きなハードルを乗り越えるための、小さな一歩として機能します。一度勉強を始めてしまえば、”せっかくだからもう少しやってみよう”と、自然と学習時間が延びていくことは珍しくありません。
- “反復”が”本物のスキル”を身につける スポーツや音楽の世界では、”反復練習”が基本です。サッカー選手が何度もドリブル練習をしたり、ピアニストが同じフレーズを繰り返し練習したりするように、反復は、脳と身体にスキルを定着させるための最も確実な方法です。 計算や漢字、英単語の暗記など、”考える”ことよりも”正確に素早くこなす”ことが求められる基礎的な分野では、ドリル学習は非常に効果的です。スポーツの”ドリル”がそうであるように、繰り返し練習することで、脳がパターンを認識し、無意識のうちに”自動化”されるようになります。
第2章:ドリル学習を”楽しむ”ための親子実践法
ドリル学習を、子どもにとって有意義な時間にするためには、親の関わり方が非常に重要です。ただ”やりなさい”と指示するのではなく、”どうすればもっと楽しくなるか”を一緒に考えることが大切です。
- ゲーム感覚でモチベーションを高める ドリル学習にゲームの要素を取り入れると、子どもは驚くほど集中して取り組みます。
タイムアタック:”この問題を5分以内に解けるかな?”と時間を測ってみましょう。”前回は4分かかったけど、今回は3分でできた!”というように、タイムを記録することで、子どもは自分の成長を”見える化”できます。 ポイント制:1ページ終えるごとにポイントをつけ、一定ポイント貯まったらご褒美をあげるルールにするなど、目標設定を分かりやすくするのも良いでしょう。
- “同じ問題”を繰り返すことの価値 “同じ問題を何度もやっても意味がない”と考える方もいるかもしれません。しかし、子どもは一度解いた問題の答えを、完璧に覚えているわけではありません。むしろ、何度も繰り返すことで、”なぜこの答えになるのか”という思考のプロセスを再確認し、より深く理解することができます。
- できない問題に固執させない ドリル学習はあくまで”成功体験”を積むためのツールです。もし子どもが、いつまでも解けない問題に直面して、”もう嫌だ!”と泣き出してしまったら、潔くその問題は飛ばしてしまいましょう。 “今はわからなくても大丈夫!できる問題からやってみようか”と声をかけ、”できる問題”に集中させることで、自信を取り戻すことができます。 また、同じドリルを何度も使う際には、”前回間違えた問題はもう一度解いてみよう”と、間違えた問題にだけ印をつけて、弱点克服に繋げる工夫も有効です。
第3章:AI時代だからこそ、人間が”努力するプロセス”を経験する意味
“将来、ドリルで身につくような知識や計算はAIがすべてやってくれる”という意見は、一理あります。しかし、”努力するプロセス”を経験することには、AIには代えられない、人間ならではの価値があります。
- 人間の”感動”はプロセスから生まれる 将棋やチェスでは、すでにAIが人間のトップ棋士を凌駕する時代です。しかし、それでも人間が将棋を指すことや、チェスをプレイすることに、私たちは感動を覚えます。それはなぜでしょうか。 それは、人間が試行錯誤し、努力する姿に心を動かされるからです。AIがどんなに正確で効率的な答えを出しても、そこには”感情”や”ストーリー”がありません。ドリル学習で”できない”から”できる”へとステップアップする過程は、子どもにとって、そしてそれを見守る親にとっても、かけがえのない”感動”となります。
- ルーティンワークの経験が創造性を育む “ルーティンワークはAIに任せればいい”と言われますが、そのAIをプログラミングするのは人間です。地道な反復作業を経験することで、人間は”効率化”のアイデアや、”新しいやり方”を発見する創造性を育むことができます。 ドリル学習を通じて、”どうすればもっと速く解けるかな?””どうすれば間違いが少なくなるかな?”と考えることは、単なる”作業”を超え、”工夫”へと繋がります。
第4章:学習は”バランス”が大切
探究学習や対話的な学び、そしてドリル学習。これらは決して対立するものではないと考えています。
ドリル学習:基礎的な知識と技能を確実に定着させ、”できる!”という自信を育む。 探究学習:身につけた知識を使って”考える力”を養い、”なぜ?”という好奇心を広げる。 これらをバランスよく組み合わせることで、子どもたちは”知識”と”思考力”の両方を効果的に伸ばしていくことができます。特に、高校受験や大学受験においても、ベースとなる知識がなければ、応用問題に取り組むことはできません。


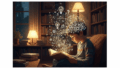
コメント