今回は「作家の時間」における「ミニレッスン」について、詳しくお話ししたいと思います。「作家の時間」は、子どもたちが自分の好きなテーマで自由に文章を書く時間です。この時間の本質は、何よりも子どもたちの「主体性」と「書くことへの楽しさ」にあります。しかし、ただ「自由に書いてね」と言うだけでは、多くの子どもが「何を書いたらいいか分からない…」と立ち止まってしまいます。
そこで重要になるのが、短い時間で、書くための技術やヒントを教える「ミニレッスン」です。
ミニレッスンは、たった10分程度の短い時間ですが、子どもたちが持つ「書きたい!」という意欲に火をつけ、その言葉を輝かせるための大切なエッセンスが詰まっています。このミニレッスンを応用すれば、ご家庭でもお子さんの書く力を自然に育むことができます。
今回は、私が特に重要だと考えている「ミニレッスン」10選を、具体的な実践方法と共にご紹介します。
第1章:ミニレッスンがひらく「作家の時間」の扉
まず、作家の時間の全体像と、ミニレッスンが果たす役割についてお話しします。
小学校の授業は通常45分です。この45分を、私は次のように構成しています。
- 最初の10分:ミニレッスン
- 先生が、書くための技術や考え方を子どもたちに伝えます。
- 次の25分:ひたすら書く時間
- ミニレッスンで学んだことを活用しながら、子どもたちがそれぞれ自分の作品をひたすら書きます。私はこの間、子どもたちの間を回って個別にアドバイスをしたり、困っている子をサポートしたりします。
- 最後の10分:共有の時間
- 自分が書いたものを誰かに読んでもらい、感想をもらう時間です。この時間は、子どもたちのモチベーションを維持する上で非常に重要です。
作家の時間は、「とにかくたくさん書く」という量を大切にしています。なぜなら、まず「書くこと」に慣れなければ、質の高い文章は生まれないからです。
第2章:作家を育むミニレッスン10選(実践編)
それでは、具体的なミニレッスンのテーマを一つずつご紹介します。
1. 「作家の時間」って何?〜学ぶ目的と授業の流れ〜
作家の時間を始める最初のレッスンです。子どもたちは、自由に書いていいと言われると驚きます。
そこで、まず「なぜこの授業をするのか」という目的を明確に伝えます。
- 「作家の時間とは、ただ好きなことを書くだけではなく、自分でテーマを考え、自分の言葉で表現する力をつけるための時間だよ」
- 「この時間を通して、みんなは自分の心を言葉にするプロになるんだ」
授業の各パート(ミニレッスン、書く時間、共有の時間)の意味を丁寧に説明することで、子どもたちはこの時間の価値を理解し、意欲的に取り組むことができます。
2. 題材を見つけるヒント
「何を書いたらいいか分からない」というのは、多くの子どもが抱える悩みです。
そこで、私は、文章の種類(物語、説明文、詩、随筆、俳句、論説文など)を提示したり、題材を見つけるためのヒントを与えたりします。
- 既存の物語をアレンジする:桃太郎の物語をベースに、登場人物を女の子に変えたり、鬼の視点から物語を書いてみたりするなど、アレンジを加えてみる。
- マッピングでアイデアを広げる:頭に浮かんだ言葉を書き出し、そこから連想する言葉を繋げていく「マッピング」という手法を教えます。これをたどっていくだけで、一つの物語や文章のアイデアが生まれます。
3. 構成をデザインする
「構成」は、文章の骨組みとなる非常に重要な要素です。
- 物語の型を学ぶ:物語には「起承転結」といった型があることを教え、教科書の短い物語を例に、それぞれの部分がどうなっているかを分析します。
- 四コマ漫画で実践:文章を書くのが苦手な子には、四コマ漫画で構成を考えるという方法も有効です。コマごとに「起・承・転・結」を絵で表現することで、物語の流れを視覚的に捉えることができます。
構成を作ってから書き始めることが必ずしも正解とは限りません。子どもたちの思考パターンは様々です。とりあえず書き始めて、後から構成を組み立てたり、直したりする柔軟性も大切にしていきたいものです。
4. 心をつかむ「書き出し」
文章の書き出しは、読者が読み進めるかどうかを決める重要な要素です。
- 書き出しのバリエーションを学ぶ:
- 疑問から始める:「あなたは〇〇を知っていますか?」
- 会話から始める:「『やった!』僕は思わず叫んだ。」
- 情景から始める:「しとしとと雨が降る、肌寒い朝だった。」
色々な書き出しの例を提示し、子どもたちに「どの書き出しが一番面白そう?」と問いかけることで、表現への関心を高めます。
5. キャラクターを掘り下げる
魅力的な登場人物は、物語に命を吹き込みます。
- 「キャラクターシート」を作る:主人公がどんな性格で、どんなものが好きで、どんな癖があるのか、詳細なプロフィールを考えるワークを行います。
- 関係性を考える:主人公とライバルの関係性、親友との関係性などを考えることで、物語に深みが生まれます。
このミニレッスンは、書く力だけでなく、他の物語を読む際にも、登場人物の心情や関係性を深く読み解く力に繋がります。
6. 情景描写で物語に奥行きを
子どもたちが書く文章は、とかく「〜しました」という行動の羅列になりがちです。
- 情景描写のワーク:
- 「窓の外を見てごらん。今、どんな景色が見える?」
- 「それを、友達に伝えるとしたら、どんな言葉で書く?」
このように、五感を意識して書くことを教えます。例えば、「悲しい気持ち」を「誰々は悲しい思いをしました」と書くのではなく、「空は鉛色に重く垂れ下がり、雨がポツポツと降り始めた」のように、情景を使って表現する方法を学びます。
7. 言葉と遊ぶ「詩と俳句」
詩や俳句は、短い言葉の中に豊かな感情や情景を凝縮する表現方法です。
- 「翻作」で言葉のセンスを磨く:既存の詩の一部を(かっこ)で空欄にし、子どもたちが自由に言葉を当てはめてみる「翻作」という手法を使います。
- 例: 谷川俊太郎さんの詩から「( )の雨が降ってくる」という部分を空欄にして、「やさしい」「さみしい」「ちいさな」など、思い思いの言葉を当てはめる。
他の作家の言葉を真似ることで、子どもたちの表現の幅は驚くほど広がります。
8. 豊かな表現を手に入れる
より豊かな表現を身につけるためのワークも行います。
- 20秒間の「動作描写」:私が教室に入ってきて、黒板の前でペンを置くまでの20秒間の動作を、子どもたちに文章で描写してもらいます。
- 問いかけ: 「先生の表情は?」「心の中では何を思っていると思う?」「この時の教室の空気は?」
- 目標: 表面に出てこない内面や、目に見えない情景までを想像して書く力を育む。
これは「書くこと」が、いかに観察力や想像力と密接に関わっているかを知る、大切なレッスンです。
9. 「推敲」で作品を磨く
自分が書いた文章を客観的に見直す「推敲」は、大人でも難しい作業です。
- 読み直す習慣づけ:
- 「声に出して読んでみると、おかしいところに気づくよ」
- 「友達に読んでもらって、分かりにくいところがないか聞いてみよう」
完璧を求める必要はありません。ただ、「一度書いたものを読み直す」という習慣をつけることが大切です。最近では、AIに文章を入れて「分かりやすくして」と頼むこともでき、子どもたちも楽しみながら推敲を行っています。
10. 「共有」が最高の褒め言葉
作家の時間の最後にある「共有」は、ただ作品を発表するだけではありません。
- 良いところを見つける名人になる:友達の作品を読んで、「この表現が面白い!」「ここ、すごく心に残ったよ!」と伝える時間を設けます。
- 「書いた甲斐があった」という喜び:自分が書いたものが誰かに伝わり、感想をもらう喜びは、子どもにとって最高のモチベーションになります。
これは、自分の作品に自信を持つだけでなく、他者の感性を尊重し、コミュニケーション能力を育むことにも繋がります。
第3章:ミニレッスンは「生きる力」を育む
ミニレッスンは、今回ご紹介した10選にとどまりません。子どもたちの「困りごと」や「興味」に応じて、テーマは常に変化します。
- 原稿用紙の使い方:正しい原稿用紙の使い方は、社会に出ても役立つ大切な知識です。
- 情報の引用と著作権:インターネットの情報をどう引用すればいいのか、著作権とは何かを教えます。
- 接続詞の魔法:「しかし」「そこで」といった接続詞が、文章の論理をどう変えるかを学びます。
これらのミニレッスンは、書く力を育むと同時に、現代社会を生き抜くための「情報活用能力」や「論理的思考力」を養ってくれます。
終わりに
作家の時間は、子どもが自ら言葉と向き合い、内なる世界を自由に表現できる、魔法のような時間です。そして、ミニレッスンは、その魔法をさらに輝かせるための道具箱のようなものです。
ぜひ、このミニレッスンのヒントを、ご家庭での親子の対話や遊びに取り入れてみてください。それは、お子さんの「好き」を言葉に変え、豊かな表現力と生きる力を育む、最高の第一歩になるはずです。

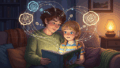

コメント