前回のブログでは、読書会が子どもの言葉の力や非認知能力をいかに育むか、その魅力についてお話ししました。
「読書会、うちの子ともやってみたい!」
そんなふうに思ってくださった方もいるかもしれません。しかし、いざ始めるとなると、「どんな本を読めばいいの?」「子どもが話してくれなかったらどうしよう?」といった不安も出てきますよね。
そこで今回は、私が小学校の教室で実践している読書会の経験をもとに、ご家庭で親子で始めるための、具体的な進め方や注意点について詳しくお伝えします。
読書会は、堅苦しいものではありません。たった5分のおしゃべりから、親子の対話はぐっと深まります。ぜひ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
第1章:読書会を成功させるための「最初のハードル」の越え方
まず、読書会を始めるときに最も大切なのは、いきなり高いハードルを設けないことです。
一冊の本を読み切るのが「最終目標」
小学校の高学年であれば、子どもは一冊の本を自力で読み切ることができるかもしれません。しかし、その上で、自分の考えをまとめ、他者の意見を聞き、さらに思考を深めるというのは、実は非常に高度な知的活動です。これは、大人でも難しいことです。
私が小学校で読書会を始める際も、いきなり一冊の本から始めることはしません。まずは教科書に載っている4〜6ページ程度の短い物語や、良質な絵本からスタートします。
- 短編から始める理由:
- 読了のハードルを下げる: 誰もが気軽に読み切ることができるため、「本を読まなければいけない」というプレッシャーがなくなります。
- 読書会の楽しさを知る: 「読書会ってこんなに楽しいんだ!」という成功体験を積むことで、次の読書への意欲が湧いてきます。
ご家庭で始める際も、いきなり分厚い小説に挑むのではなく、お子さんが「これなら読めそう!」と思えるような、身近な絵本や短編から始めてみてください。
最初は「5分のおしゃべり」で十分
読書会の時間も、最初から長く設定する必要はありません。
小学校の教室では、まず15分程度を目標に、4人グループで話し合いを行います。それでも、最初から15分間も話が続く子どもたちは、決して多くありません。
ご家庭で親子2人で行うのであれば、最初の目標は「5分間のおしゃべり」で十分です。
- 質より「楽しかった」という記憶:
- 「パパ(ママ)と本について話せて楽しかったな」
- 「この本、すごく面白かったね!」
- このポジティブな感情が、次の読書への最高のモチベーションになります。
読書会のクオリティは、継続していくうちに自然と上がっていくものです。まずは「楽しさ」を最優先に考えてみてください。
第2章:読書会の「はじめ方」〜親が示す最高のモデル
読書会を始める際、親の振る舞い方が非常に重要になります。子どもに「話しなさい」と促すのではなく、まず親が「こういう風に話すんだよ」「こういう風に聞くんだよ」というモデルを示すことが大切です。
1. まずは「あらすじ」を言葉にする
読書会を始める最初のステップは、「どんなお話だったか」をお子さんに話してもらうことです。
- 問いかけ: 「この本、どんなお話だったかな?」
- 親の応答: お子さんが話している間は、相槌を打ち、笑顔で頷きながら聞きます。話が終わったら、「すごいね!あらすじがすごくよくわかったよ」と、しっかりと価値づけてあげてください。
「ちゃんと聞きなさい」という言葉だけでは、子どもは「ちゃんと聞く」がどういうことかイメージできません。親が最高の聞き役のモデルになることで、子どもは「聞く力」を自然と学んでいきます。
2. 親が率先して「自分の感想」を話す
次に、親が自分の感想を話す番です。子どもに「何か感想はある?」と聞くのではなく、まずは親がモデルになってみましょう。
- 問いかけ: 「パパ(ママ)は、この登場人物のこういうセリフがすごく面白かったな。思わず笑っちゃったよ。あなたは?」
- 親の応答: 自分の感想を話すことで、「こういう風に話せばいいんだ」という具体的な例をお子さんに示すことができます。
最初は「面白かったところ」や「笑ったところ」など、感情的な部分から入ると、子どもも話しやすくなります。
3. 「分からない言葉」を一緒に探す
絵本や物語の中には、子どもにとって理解が難しい言葉が出てくることがあります。
- 問いかけ: 「この言葉、なんだか難しかったんだけど、あなたはどうだった?」
- 親の応答: 分からない言葉を一緒に調べてみましょう。これは、お子さんの語彙力を増やす最高の機会になります。
「分からないこと」を恥ずかしいと思うのではなく、「分からないことを知るのが面白い!」と感じさせることで、子どもは自ら学びに向かう姿勢を身につけていきます。
第3章:読書会を「対話」に変える魔法の質問
あらすじや感想を話し合った後、さらに会話を深めるためには、親からの少し踏み込んだ「問い」が効果的です。
1. 本と「自分の体験」を結びつける
読書の最大の喜びは、本の内容を自分の人生と重ね合わせることです。
- 問いかけ: 「この物語に出てくる登場人物みたいに、〇〇もそういう経験ってあった?」
- 親の応答: 親が先に「私もね、実は似たような経験があって…」と話すことで、子どもは安心して自分の体験を話せるようになります。
普段の何気ない会話の中では聞けないような、お子さんの心の中にある感情や体験を知る、貴重な機会になるでしょう。
2. 本を「多角的に」捉える
読書会は、本の内容を深く考えるためのトレーニングでもあります。
- 問いかけ:
- 「もし、このお話の登場人物が入れ替わったらどうなると思う?」
- 「この物語の続きは、どんなふうになるだろう?」
- 「この物語のテーマって、何だと思う?」
これらの問いは、お子さんの思考力を刺激し、物語を立体的に捉える力を育んでくれます。
第4章:読書会を継続させるための工夫
読書会を単発で終わらせず、親子間のルーティンにするためには、いくつかの工夫が必要です。
1. 「自己決定」がモチベーションを高める
次に読む本は、必ずお子さんに選ばせるようにしましょう。
- ポイント: もしお子さんが本をあまり読まない場合でも、「この5冊の中からだったら、どれがいい?」と、選択肢を限定して選ばせてみてください。
自分で選んだ本であれば、子どもは「やらされ感」ではなく、「自分で決めた!」という強いモチベーションを持って読書に臨めます。
2. 読書会は「なんでもあり」
「読書会」の題材は、物語や絵本に限定する必要はありません。
- 電車の図鑑で読書会: 電車が好きなお子さんなら、電車の図鑑を題材にしてみましょう。「この電車はどんな特徴があるの?」「この電車の歴史って?」など、図鑑を読み解きながらおしゃべりすることで、それは立派な読書会になります。
- 辞書で読書会: 辞書から興味のある言葉を探し、その意味について語り合うのも面白いでしょう。
大切なのは、「本」を介して、親子で楽しく言葉を交わすことです。
3. 「記録」を残して、自信につなげる
読書会が終わった後、感想や気づきを記録に残してみましょう。
- 手書きの読書ノート: 日付、本のタイトル、感想などを手書きで記録することで、お子さんの自信につながります。
- AIを活用した音声入力: 「書くのが苦手」というお子さんには、スマートフォンの音声入力機能を使い、感想を話してもらいましょう。その内容をAIに要約してもらうことで、手軽に記録を残すことができます。
この記録は、お子さんが「こんなにたくさんの本を読んだんだ!」という達成感を得るための、大切な宝物になります。
【親子で始めるブッククラブにおすすめの絵本5選】
ここからは、ご家庭での読書会にぴったりな、短いけれど深い絵本を5冊ご紹介します。
- 『おおきな木』 / シェル・シルヴァスタイン: 与えることの喜びと、受け取ることの感謝について深く考えさせられる物語です。
- 『じぶんだけのいろ』 / レオ・レオニ: 自分らしさや、ありのままの自分を受け入れることの大切さを、美しい絵と短い言葉で伝えてくれます。
- 『ちいさなやさしさ』 / エミリー・グラヴェット: 普段見過ごしてしまいがちな「やさしさ」を、ユーモラスに描いています。
- 『100万回生きたねこ』 / 佐野洋子: 生きること、そして愛することの意味について、親子でじっくり話し合うきっかけを与えてくれます。
- 『ふたりはともだち』 / アーノルド・ローベル: 仲良しのがまくんとかえるくんを通して、友情や思いやりについて考えさせられる物語です。
終わりに
読書会は、お子さんの読解力や表現力を育むだけでなく、親子の間に「心の対話」を生み出してくれます。
ぜひ、身近な本を手に取って、お子さんと一緒に「おしゃべり」を楽しんでみてください。それが、読書を好きになり、言葉の力を伸ばす、最高の第一歩になるはずです。


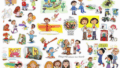
コメント