「うちの子、全然本を読まないんです。スマホばっかり触ってて・・」
保護者の方と話していると、そのような声をよく聞きます。活字離れが進む現代において、子どもが本に興味を持たないのは、決して珍しいことではありません。しかし、読書や言葉の学びは、子どもの成長にとって欠かせない大切な活動です。私は、子どもたちが「楽しい!」と感じることで、自ら言葉の世界に飛び込めるようになると信じています。
そこで今回、私が小学校の教室で実践している「読書会(ブッククラブ)」について、その効果や具体的な方法を詳しくお伝えしたいと思います。
「読書会なんて、なんだか堅苦しそう…」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、読書会は、本をきっかけに「おしゃべりを楽しむ」時間です。ご家庭でも気軽にできる、親子間の対話を深めるツールにもなると思います。
第1章:「読まされ感」からの脱却〜なぜ今読書会なのか?
小学校の国語の授業は、教科書に載っている物語や説明文を、クラス全員で読み進めていくのが一般的です。もちろん、このやり方にも良い点はたくさんあります。しかし、私はこの一斉授業の形式に、いくつかの課題を感じていました。
従来の授業が抱える「30人中20人が置き去り」問題
クラスに30人の子どもがいるとします。先生が発問したとき、積極的に手を挙げて発言するのは、いつも決まった10人程度の子どもたちだったりします。
この10人が活発に発言することで、授業は一見、盛り上がっているように見えます。しかし、残りの20人はどうでしょうか。
- 「つまらないな…」と感じながら、ただ座っている子。
- 「何を話しているのか、全然わからない…」と置き去りにされている子。
- 「発言したいけど、自信がないからやめておこう…」と、自分の考えを心の中にしまってしまう子。
こうした子どもたちは、読書を通して、あるいは授業を通して、本当に自分の言葉で考える機会を得ているとは言えません。教師として、すべての子どもが主体的に学びに参加できる場を作ることが、私の長年の課題でした。
読書会が解決する「置き去り」問題
この課題を解決するために、私が実践しているのが「読書会(ブッククラブ)」です。
読書会は、クラスを4人程度の小さなグループに分け、それぞれが同じ本を読んで、その内容について話し合う活動です。4人という少人数だからこそ、すべての子どもに「話す時間」が確保されます。
- 「話すことが苦手…」と感じている子も、少人数なら安心して発言できます。
- 積極的に発言しない子も、友達の意見を聞きながら、自分の考えをゆっくりと形にできます。
読書会は、子どもたちを「授業のお客さん」にせず、一人ひとりが「学びの主人公」になれる場なのです。
読書会のハードルを下げる工夫
読書会を成功させるには、まず「本を読み終えること」が最初のハードルになります。
そこで、私は子どもたちが無理なく読書会に参加できるように、題材を工夫しています。
- 絵本: ページ数が少なく、内容も分かりやすい絵本は、読書が苦手な子どもでも、全員が読了するハードルをぐっと下げてくれます。絵から様々な感情や物語を読み取る練習にもなります。
- 短編小説: 森絵都さんなどの、心に響く良質な短編小説もよく使います。ページ数が20ページ程度のものを選べば、集中して読み切ることができます。
子どもたちに「自分で本を選びたい!」という気持ちが芽生えたら、教師が用意した5〜6冊の中から自由に選ばせることで、「読まされ感」ではなく「自分で決めた」という主体性を育むことも大切にしています。
第2章:読書会を成功に導くための「場づくり」と「教師の役割」
読書会を効果的な学びの時間にするためには、いくつかの工夫が必要です。教師として、私は主に「場づくり」と「子どもをサポートする役割」に徹します。
1. 読書会の土台となる「聞く力」を育む
読書会では、話す力と同じくらい「聞く力」が重要です。
- 最後まで聞く: 友達が話している間は、決して遮らず、最後まで耳を傾けることを徹底します。
- 頷きながら聞く: 相手に「あなたの話を聞いていますよ」というメッセージを伝えるために、頷きや相槌を打つことを促します。
- 相手の目を見て聞く: 相手の目を見て話を聞くことで、真剣に聞いている姿勢が伝わり、話し手は安心して意見を述べることができます。
「聞いてもらえる」という安心感があるからこそ、「話したい」という気持ちが生まれます。こうした土台を丁寧に作ることが、読書会の成功には不可欠です。
2. 「自分の考え」をまとめるアウトプットの習慣
読書会は、ただ本を読んだだけで参加するものではありません。子どもたちには、事前に本を読み、自分の考えをまとめるアウトプットの時間を与えます。
- 付箋を使ったまとめ: 「この主人公の行動について、こう思った」
- メモ帳への書き出し: 「この物語のテーマは〇〇だと思う」
こうしたアウトプットを事前に行うことで、読書会で話す内容が整理され、より深い議論へと発展させることができます。
3. 教員ブッククラブで学び続ける
私自身も、教員仲間と定期的に「ブッククラブ」を行っています。その時のやり方は、子どもたちの読書会にも応用できるヒントがたくさん詰まっています。
- 3分間の発表時間: まず、共通して読んだ本について、全員が3分間、自分の感想を自由に話す時間を設けます。これは野球の打順のように、必ず全員に回ってきます。自分の番が必ず来るという意識が、参加意欲を高めてくれます。
- 「問い」の共有: 話し合いを深めるために、各自が「この部分がよく分からなかった」「この表現が印象に残った」といった「問い」を持ち寄り、そこから対話を広げていきます。
この教員ブッククラブでの経験が、子どもたちの読書会をより豊かにするためのヒントになっています。
第3章:読書会が育む「言葉の力」と「聞く力」の相乗効果
読書会がもたらす最大の効果は、教科書の内容を理解することだけにとどまりません。子どもたちの言葉の力、そして人間関係を築く力を総合的に育んでくれます。
1. 「話す力」の土台を築く
読書会では、自分の考えを自分の言葉で話す機会が必ず訪れます。これは、単なる感想文の発表とは全く異なります。
- 思考の言語化: 「この主人公の気持ちは…」と考えたことを、どう言葉にすれば相手に伝わるかを試行錯誤することで、思考を言語化する力が養われます。
- 他者からの影響: 友達の意見を聞き、「なるほど、そういう考え方もあるのか!」と気づくことで、自分の考えを修正したり、さらに深めたりする力が育まれます。
2. 「聞く力」が「共感力」を育てる
読書会は、友達の話を「聞く」ことで、自分とは異なる価値観や考え方に触れる貴重な時間です。
- 他者の視点: 同じ本を読んでいても、子どもたちの感想や感じ方は一人ひとり異なります。友達の意見を聞くことで、「同じ文章を読んで、こんなに違う考え方があるんだ!」という驚きと発見が生まれます。
- 読解力への影響: 友達の意見を聞いて、物語の解釈が深まることも多々あります。これは、国語の授業で求められる「読解力」を、受け身ではなく、主体的に高めていくことに繋がります。
3. 「体験」と結びつける力
読書会では、本の内容について話すだけでなく、それを「自分の体験」と結びつけて話すことがよくあります。
- 自分自身の体験: 「この本を読んで、僕も昔こんなことがあったのを思い出したんだ」
- 読書体験: 「この本に出てくる〇〇って、前に読んだ別の本にも出てきたな」
このように、本の内容を自分自身や他の本と繋ぎ合わせることで、子どもたちは知識を点と点で結びつける力を身につけ、物事を多角的に捉える思考力を養っていきます。
第4章:親子で楽しむ「おしゃべり読書会」のすすめ
「読書会」というと、堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、ご家庭で実践するのはとてもシンプルです。
大切なのは、「本を介して、おしゃべりを楽しむ」こと。映画や音楽について親子で語り合うのと同じ感覚で、本を「おしゃべりのきっかけ」にしてみてください。
家庭で実践するための3つのステップ
- 同じ本を読んでみる: まずは、親子で同じ本を読んでみましょう。絵本、児童文学、短編小説、何でも構いません。同じ物語を共有することで、深い対話の土台ができます。
- 親子で「問い」を持つ: お子さんだけではなかなか感想が出てこないこともあるでしょう。そんなときは、お母さんやお父さんの方から「問い」を投げかけてみてください。
- 例: 「この主人公の行動、ママはちょっと理解できなかったんだけど、あなたはなぜだと思う?」
- 例: 「この物語に出てきた『〇〇』っていう表現、どういう意味だろうね?」
- 例: 「もし、このお話の登場人物が入れ替わったら、どうなると思う?」 こうした問いは、子どもの思考を刺激し、対話をスムーズに進めてくれます。
- 互いの「人間理解」を深める時間にする: 読書会は、本をきっかけに、普段は話さないような深い話ができる絶好の機会です。
- お子さんが、「この部分、自分も同じ経験があって…」と話してくれるかもしれません。
- お母さんやお父さんも、「実は昔、こんなことを考えていたんだ」と自分の価値観を話してみるのも良いでしょう。
読書会を通して、「この子はこんなことを考えているんだ」「お母さん(お父さん)は、こんなことを大切にしているんだ」というお互いの発見が生まれます。これは、親子間の人間理解を深める、とても貴重な時間になるはずです。
終わりに
読書会は、本の内容を深く理解するだけでなく、自分の言葉で表現する力、他者の意見に耳を傾ける力、そして何より、家族の絆を深める「対話の力」を育むことができます。「本を読んだら、おしゃべり」このシンプルな習慣が、お子さんの未来を豊かにする力になります。ぜひ、ご家庭で親子一緒に、読書会を楽しんでみてください。

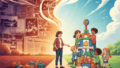
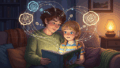
コメント