前回は、論説文を読み解くための基礎として、「要旨の把握」や「はじめ・中・終わりの構造」についてお伝えしました。今回はさらに一歩踏み込み、より複雑な論説文を読み解くための「応用編」をお伝えします。
応用編と言っても、基本の読み方は変わりません。しかし、文章が複雑になると、ただ読むだけでは筆者の意図を見失いがちです。そこで、今回は文章の奥にある**「隠された構造」**を見抜くための3つの鍵について、具体例を交えながら解説していきます。
応用編で扱うような複雑な論説文を読み解くには、まず高い語彙力があることが前提となります。抽象度が高い専門的な語彙が増えるため、分からない言葉が多すぎると、いくら構造を理解しようとしても、内容が頭に入ってきません。
しかし、語彙力がある上でこの3つの鍵を意識することで、読解力は飛躍的に向上します。
複雑な論説文を読み解く3つの鍵
1. 具体と抽象:行ったり来たりする思考の往来
論説文は、**「抽象的な概念」と、それを分かりやすく説明する「具体的な事例」**で構成されています。この2つを行き来する筆者の思考を読み解くことが、文章の本質を理解する上で非常に重要です。
- 抽象的な言葉(概念):
- 例: 「多様性」「グローバル化」「持続可能性」「効率化」「本質」
- 特徴: 目に見えない、概念的な言葉。筆者の主張や論の骨子となる部分に多く使われます。
- 具体的な言葉(事例):
- 例: 「スマートフォン」「日本の農業」「電気自動車」「工場の生産ライン」「子どもの声」
- 特徴: 目に見える、体験できる、具体的な事柄。抽象的な概念を分かりやすくするために使われます。
筆者は、まず抽象的な概念を提示し、次にそれを補足する具体的な事例をいくつか並べることがよくあります。
【具体例】
抽象(主張): 現代社会では、**「多様性」**を尊重する姿勢が求められている。
具体(説明): 例えば、職場では国籍や性別に関係なく誰もが活躍できる環境を整えたり、学校では生徒一人ひとりの個性を伸ばす教育が重視されたりする。つまり、社会全体が単一的な価値観から脱却し、さまざまな違いを認め合う方向へと変化しているのだ。
この例のように、「例えば」「具体的には」といった接続詞は、抽象から具体へと話が移るサインです。逆に、「つまり」「要するに」といった接続詞は、具体から抽象へと戻るサインとなります。これらのサインを見つけながら、筆者が今、全体的な主張(抽象)を述べているのか、それとも具体的な補足説明(具体)をしているのかを意識して読み進めると、文章の構造が見えてきます。
要約する際は、この抽象と具体の関係を理解し、具体的な部分は削り、最も抽象度の高い筆者の主張を抜き出すことが重要になります。
2. 対比構造:主張を際立たせる「比較」の力
論説文の書き手は、自分の主張をより説得力のあるものにするために、**「対比構造」**を用いることがあります。これは、正反対の意見や、異なる事柄を並べて比較することで、自分の主張の正しさを強調する手法です。
- 「A」という主張を立てる。
- 「一方で、Bという主張もある」と、あえて反対意見を紹介する。
- 「しかし、Bにはこのような弱点がある」と反論する。
- 「だから、やはりAが正しいのだ」と結論づける。
このパターンは非常に多く、この構造を見抜くことで、筆者が本当に伝えたいことは何かを正確に掴むことができます。
【具体例】
筆者の主張(A): 子どもの読書は、紙の本でなければならない。
対立意見の提示(B): 一方で、電子書籍の普及により、近年では「読書はデジタルでも良い」という声も増えている。
反論と再主張(A): しかし、電子書籍は画面からブルーライトを発し、子どもの視力に悪影響を及ぼすという問題がある。また、紙の本のように手でめくる感触や、インクの匂いといった五感に訴える体験が少ない。したがって、読書の楽しさや集中力を育むためには、やはり紙の本が優れているのだ。
このように、「一方で」「しかし」「だが」といった逆接の接続詞は、対比構造のサインとなります。このサインを見逃さずに、筆者が「対比」の対象として挙げたものが、実は筆者自身の主張を強めるための「引き立て役」であることを理解することが、読解力の鍵となります。
3. 関連構造:文章の「因果関係」をたどる力
論説文は、個々の文章や段落がバラバラに存在するのではなく、**論理的な「関連」**で結びついています。この関連を読み解く力は、物事の因果関係を把握する力そのものです。
この関連構造を読み解く手がかりとなるのは、指示語と段落間の役割です。
- 指示語: 「これ」「それ」「あれ」「この」「その」など。これらの言葉が何を指しているかを正確に把握することが重要です。
【具体例】
A. 筆者は、読解力向上のために「多読」が不可欠だと主張している。 B. これは、文章に多く触れることで、無意識のうちに語彙力や読むスピードが向上するからだ。
この場合、「これ」が指しているのは、前の文で述べられた**「多読が不可欠だという主張」**です。このように、指示語は、文章同士の関連性を明確に示しています。
- 段落間の役割: 論説文の各段落は、それぞれ役割を持っています。
【具体例】
- 第1段落: (導入・問題提起)
- 第2段落: (原因・理由)
- 第3段落: (具体例)
- 第4段落: (解決策・提言)
文章が複雑になると、第2段落で述べた内容に対して、第3段落で反論を述べ、第4段落でその反論に対する反論を述べる、といった複雑な構成になっていることもあります。この「因果関係」や「役割」を意識しながら段落を読み進めることで、文章全体がどのような論理で組み立てられているかという、筆者の「思考の地図」を頭の中で再構築することができるのです。
AIを「コーチ」として活用する
これらの応用的な読み方は、慣れないうちは難しく感じるかもしれません。そんなときは、ぜひAIをコーチとして活用してみてください。
- AIに文章を読み込ませる: 読解が難しい論説文をAIに読み込ませます。
- 「コーチング」を依頼する: プロンプトに、**「この文章の読解コーチになってください。具体と抽象の構造、対比構造、関連構造(因果関係)について、段落ごとに分かりやすく解説してください」**と指示します。
- 答え合わせをする: AIが提示した解説と、自分で考えた構造を比較し、なぜそのように読み解くのかを学ぶことで、読解力を効率的に高めることができます。
これは、塾で個別指導を受けるのと同じような効果を、ご家庭で手軽に得られる画期的な方法です。AIに頼りきりになるのではなく、あくまで自分の思考を補助し、学ぶための強力なツールとして活用することが重要です。
まとめ:論説文は「骨組み」を読み解くパズル
論説文の読解は、筆者が組み立てた「文章の骨組み」を、読み手がいかに正確に再構築できるかというパズルに似ています。
- 具体と抽象で、筆者の主張と具体例を区別する。
- 対比構造で、筆者が本当に伝えたいことを見極める。
- 関連構造で、文章全体の因果関係をたどる。
これらの「鍵」を意識しながら読み進めることで、どんなに複雑な文章であっても、その「設計図」が見えてくるようになります。この力は、受験や社会に出てからも、論理的に思考し、深く理解するために不可欠なスキルです。
次回予告:物語文の読解力向上法
今回は論説文の応用編をお伝えしました。次回は、読解力向上の最後のテーマとして、**「物語文」**の読み方について解説していきます。物語文は、登場人物の心情や情景描写を読み取ることが中心となりますが、そこにも論理的な読解のコツがあります。
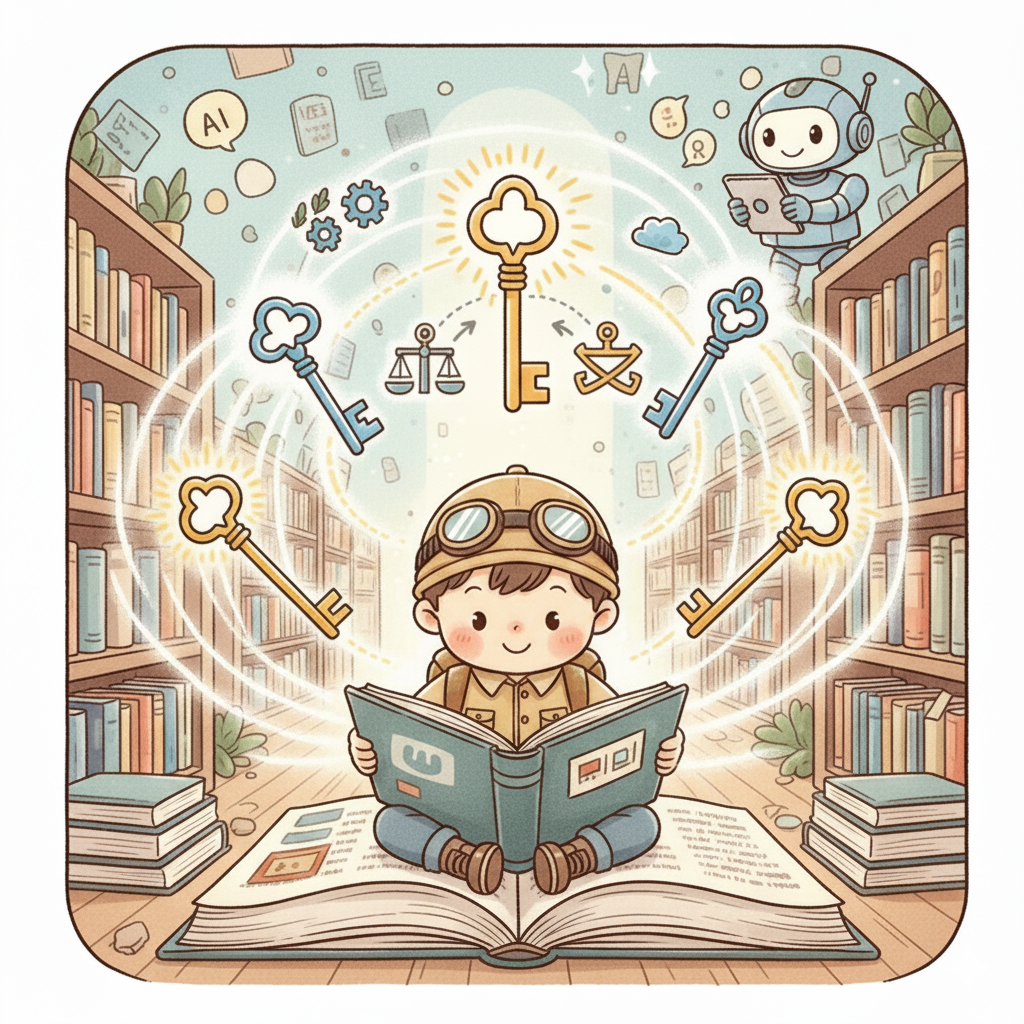


コメント