子どもたちの周りには、学びの種が驚くほどたくさん埋まっています。そんな学びの種をもとに「問い」を見つけて探究していく力が、生きる力につながっていきます。今回のブログでが日常体験を学びに変える方法についてご紹介します。
第1章:今、求められる学力とは?
かつて、学力は「どれだけ多くの知識を記憶しているか」で測られていました。しかし、現代社会は大きく変わり、入試もまた、その変化に対応しています。
今、大学入試や高校入試で問われているのは、単なる知識の量ではありません。
- 思考力:物事を多角的に捉え、深く考える力
- 表現力:自分の考えを、論理的かつ豊かに伝える力
- 探究心:未知の事柄に対し、自ら「なぜ?」という問いを立て、答えを追求する力
これらの力は、教科書を読んだり、問題を解いたりするだけではなかなか身につきません。
AIが膨大な知識を瞬時に処理できる時代に、私たち人間にしかできないことは何でしょうか?それは、「心が動く体験」から生まれる、唯一無二の「自分だけのストーリー」を語ることです。
日常の何気ない体験も立派な体験です。五感を使い、人と出会い、対話することで、子どもたちは自分の中に、誰にも真似できないストーリーの種を見つけていくのです。
第2章:日常を「探究」に変える
冒頭でお伝えしたように、日常は学びの種にあふれています。大切なのは、「そこに学びの種が埋まっている」という視点を大人が持つこと。そして、その種に光を当てることです。
1. 散歩が最高の探究活動になる
いつもの散歩道が、最高の探究フィールドになります。学びの種を探す、という意識をもつだけで、これまで目に入らなかった景色が目に入ってきます。いくつか例をご紹介します。
- マンホールの柄: 「ねえ、このマンホールの柄、何が描いてあるか知ってる?」
- お子さんがマンホールの柄に興味を持てば、「どうしてこの町は、こんな絵柄を使っているのかな?」「水道局のマークかな?それとも、その町のシンボルかな?」と、探究の扉が開きます。
- 電車の色: 「この電車、なんでこんなにカラフルなのかな?」「他の国の電車はどんな色をしているんだろう?」
- 看板の文字: 「このお店の看板の文字、なんだか面白い形だね。どうやって書いているのかな?」
ほんの少し、大人が「あれ、面白いね」と声をかけるだけで、子どもたちの好奇心は刺激され、何気ない日常が、学びと探究の時間に変わります。
2. 親の仕事は最高の「生きた教材」
お子さんに、お父さんやお母さんの仕事についてインタビューさせてみるのはいかがでしょうか。
「パパ(ママ)の仕事って、何をしているの?」
きっと、子どもからはこんな質問が飛び出してくるはずです。
- 「金融って何?」
- 「貿易ってどういうこと?」
- 「なぜ日本の車は世界中で人気なの?」
これらの問いに答えることは、社会の仕組みや経済の動き、グローバルな世界を子どもに伝える最高の機会になります。親自身が、子どもにとって「本物の教材」になるのです。
3. 体と五感を使った遊び
勉強といえば、机に向かうことだと思われがちですが、五感をフル活用する遊びは、脳と心を育む最高の学びの種です。
- 体を動かす遊び:鬼ごっこ、サッカー、キャッチボール。
- 「やった!」「くやしい!」といった感情が、体を通して心に深く刻まれます。
- チームで勝利した喜びや、負けた悔しさ、友達と協力する大切さなど、教科書では学べない学びがここにあります。
- 家事:料理や片付け
- 料理:食材を触り、匂いを嗅ぎ、味を感じる。分量を測るときは算数を使い、レシピを読み解くときは国語を使います。
- 片付け:どうすれば効率よく片付けられるかを考えることで、論理的思考力が養われます。
子どもたちが夢中になって遊んだり、家事をお手伝いしたりする中で、心が動く瞬間に、ぜひ注目してみてください。
第3章:体験を「概念」に変える親子の対話術
ただ体験するだけでなく、その体験を「自分自身の言葉で振り返り、整理すること」が、学びを定着させる上で最も重要です。このプロセスこそが、体験を「生きる力」に変えていきます。
1. 「メタ認知」で自分を知る
「メタ認知」とは、「自分自身を客観的に見つめ直す力」のことです。
例えば、サッカーの試合に負けて悔しがっているお子さんへの声かけもメタ認知のきっかけになります。
- 第一段階:事実の言語化
- 「今日の試合、どうだった?」
- 「うん、負けて悔しかった」
- 第二段階:感情の言語化
- 「どうして悔しかったの?」
- 「最後のシュートを決められなかったから」
- 第三段階:メタ認知
- 「その『悔しい』って気持ち、どんな時に感じる?」「他の場面で悔しいと思ったことはある?」
- この問いかけは、「シュートを外したこと」という特定の出来事から、「努力が実らなかった時の気持ち」という普遍的な感情へと、思考を広げてくれます。
2. 「汎用的な概念スキル」を身につける
このメタ認知の対話を通して、子どもたちは特定の体験から、どんな状況にも応用できる「汎用的な概念スキル」を身につけていきます。
- 例えば、スポーツの体験から…
- 「努力すれば報われる」
- 「チームで協力すれば、一人ではできないことができる」
- 「負けた悔しさを、次に活かす」
- 例えば、料理の失敗から…
- 「手順を間違えると、うまくいかない」
- 「分量を正確に測ることの大切さ」
- 例えば、ケンカから…
- 「言葉を選ばないと、相手を傷つけてしまう」
- 「違う意見でも、話し合えば分かり合える」
これらの概念は、スポーツだけでなく、勉強、友人関係、そして将来の仕事など、あらゆる場面で役立つ「生きるための知恵」となります。
第4章:教室で実践
教室では子どもたちが本物体験をできるような工夫を考えています。
- 具体物との対話
- 例えば、国語の授業で「春の七草」を学ぶとき、私は本物の七草を教室に持ち込みます。子どもたちは、匂いを嗅ぎ、葉っぱの形を観察し、実際に触れることで、言葉だけでは得られない「本物の学び」を体験します。
- ITを活用した人との出会い
- ITが発達した現代では、Zoomなどを使い、全国各地の人々と繋がることができます。北海道の農家の方に野菜づくりの苦労を聞いたり、遠方の企業で働くエンジニアの方に、仕事のやりがいを語ってもらったり。
- 画面越しの出会いであっても、子どもたちの「なぜ?」という問いに、その道のプロが答えてくれる。これは、彼らの学びを「リアルなもの」に変える、最高の体験です。
終わりに
このように学びの種は日常にあふれています。学びの種を見つける意識と、お子さんがそれを探究していくためのサポートや、メタ認知を促す対話を通して、学びの種を汎用的な概念を獲得する学び変えることができます。ぜひ、今日から、お子さんと一緒に散歩に出かけたり、料理をしたり、公園で思いっきり体を動かしたりしてみてください。そして、その体験を振り返る時間を、少しだけ取ってみてください。その何気ない対話が、お子さんの人生を豊かにする学びへの第一歩になることを、心から願っています。

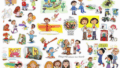

コメント