いつもブログをお読みいただきありがとうございます。 このブログでは、ご家庭で日々お子さんの教育と向き合っていらっしゃる保護者の方に、少しでもお役に立てる情報を発信しています。
「作家の時間」をテーマにしたこの連載では、子どもたちが「書くこと」を心から楽しみ、その力を自然に伸ばしていけるようなヒントをお届けしています。前回は、文章の第一歩となる「書き出し」についてお伝えしました。
今回は、その次のステップ、「物語の構成」についてお話しします。
「いきなり書き始めるのではなく、構成をしっかり考えてから書きなさい」
これは作文指導の正攻法としてよく言われることですが、書くことが苦手な子どもたちにとっては、時に大きなハードルになってしまうこともあります。
小学校でも、付箋を使って場面ごとに書くことを整理し、その順番を並べ替えるという方法がよく使われています。しかし、私はこのブログでは「書くのが苦手な子」が「書きたい!」と思えるようになることを目指しているので、子どもたちの脳の仕組みに合った、もっと自然な構成の考え方をお勧めしています。
それが、「マッピング法」です。
マッピング法は、子どもの自由な発想を邪魔することなく、物語をどんどん膨らませていくことができる、とても効果的な方法です。この記事を読み終える頃には、お子さんの作文指導がもっと楽しくなるヒントが見つかるはずです。
付箋法とマッピング法、それぞれの特徴
まず、学校でよく使われる付箋法と、私が特にお勧めするマッピング法について、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 構成法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 付箋法 | 小さな付箋に場面ごとの出来事を書き出し、並べ替える方法。 | 構成が視覚的に分かりやすく、順番を自由に変えやすい。 | 発想がまとまりにくく、苦手な子にとっては「面倒くさい」と感じることがある。 |
| マッピング法 | 中心にテーマを書き、そこから連想する言葉や場面を放射線状に広げていく方法。 | 脳の構造と似ており、自然にアイデアが湧きやすく、思考が広がりやすい。 | 付箋ほど細かな場面の並べ替えは得意ではない。 |
どちらの方法も一長一短ありますが、私は特に、「まずアイデアをたくさん出す」という段階においては、マッピング法が人間の脳の働きにとても合っていると感じています。
【実践編】マッピング法で物語を構成してみよう
では、実際にマッピング法を使って物語の構成を考えてみましょう。準備するものは、大きな紙と鉛筆、そして色鉛筆だけです。
ステップ1:中心にテーマを置く
まず、紙の真ん中に物語のテーマを書き、丸で囲みます。 例えば、今回は「冒険物語」というテーマで進めてみましょう。
ステップ2:思いついたことをどんどん繋げる
次に、中心の丸から線を引いて、思いついたことをどんどん書き出していきます。この時、どんな小さなアイデアでも、思いついたままに書き出すことが大切です。
例えば、「登場人物」「場面」「出来事」など、思いついた項目を書き出します。
ステップ3:項目をさらに深掘りする
次に、書き出した項目からさらに線を引いて、詳細なアイデアを加えていきます。
- 登場人物
- 線を引いて「主人公」「主人公の友達」「脇役」などと書き出す。
- 「主人公」からさらに線を引いて、「12歳の男の子」「サッカーが大好き」「とても心優しい」など、キャラクターの特徴を細かく書き出していく。
- 場面設定
- 線を引いて「学校」「夏休み」「海」などと書き出す。
- 「学校」からさらに線を引いて、「教室」「下校中」など、具体的な場所をイメージしていきます。
このように、まるで木の枝が広がるように、アイデアをどんどん繋げていきます。
【応用編】マッピング法でストーリーを深めるコツ
ただアイデアを書き出すだけでなく、マッピング法をさらに活用して、物語をより魅力的にする方法をご紹介します。
1. 起承転結を意識して展開を繋げる
物語の構成には、「起承転結」という有名な型があります。マッピング法でも、この流れを意識してアイデアを繋げていくことができます。
- 起 (始まり):物語のきっかけとなる出来事。「学校で友達とどこかに行こうと話している」「宇宙人と出会う」など。
- 承 (展開):物語が動き出す部分。宇宙人に助けを求められ、みんなで宇宙船に乗って旅に出る。
- 転 (変化):物語の大きな変化点。敵が実は「蟻族」という大群で、どう戦うかという問題に直面する。
- 結 (結末):問題が解決し、物語が終わる部分。たまたま持っていた殺虫剤で蟻族を撃退し、宇宙人を助ける。
このように、マッピング上で起承転結の流れを書き出すことで、物語の骨組みが自然に完成します。
2. テーマに合わせて「成長」を描く
マッピングのアイデアを繋げた後、「この物語で、登場人物はどう成長したかな?」と考えてみましょう。
- 冒険を通して、主人公と友達の「友情の絆」が深まった。
- 臆病だった主人公が、勇気を出して前に進めるようになった。
こうしたテーマを決めることで、ただの出来事の羅列ではなく、深みのある物語へと変わっていきます。
パソコンを活用するメリット:書くことがもっと身近に
手書きで作文を書くのももちろん素晴らしいですが、特に「構成」を考える際には、パソコンを使うこともお勧めします。
- 簡単に修正・追加ができる:手書きの場合、構成を変えたくなったら最初から書き直さなければなりません。しかし、パソコンなら切り取りや貼り付けで、簡単に場面を入れ替えることができます。
- 思考を中断せずに書ける:書きながら「やっぱりこの場面を先に入れたいな」と気づくことはよくあります。パソコンなら、すぐに修正できるので、思考の流れを止めずに書き進められます。
子どもたちが「また書き直さなきゃいけないの?」と作文を嫌いになってしまうことを防ぐためにも、パソコンは強い味方になります。
マッピング法以外の文章構成法
マッピング法の他にも、文章の構成を考えるための効果的な方法がいくつかあります。
- ブレインストーミング法:
- 方法: 時間を区切って、とにかく思いつく言葉やアイデアを紙に書き出していく方法。アイデアの質は問わず、量を出すことを目的とします。
- 特徴: 最初のアイデア出しに特に有効です。マッピング法と組み合わせて使うと、さらに効果的です。
- プロットライン法:
- 方法: 物語の始まりから終わりまでを、一本の線で表現する方法。線の起伏でストーリーの盛り上がりや変化を表し、そのポイントごとに出来事を書き込みます。
- 特徴: 感情の起伏や物語のテンポを視覚的に捉えやすく、物語全体を俯瞰して見ることができます。
これらの方法も、お子さんのタイプや書く文章の種類に合わせて、ぜひ試してみてください。
まとめ:構成は「設計図」、自由な発想を大切に
文章の構成を考えることは、家を建てる際の「設計図」を作るようなものです。
しっかりとした設計図があれば、迷わずに家を建てることができます。しかし、設計図はあくまで「計画」であり、途中で「やっぱりここに窓をつけたいな」と思ったら、変更しても大丈夫です。
大切なのは、「完璧な構成」を最初に作ることではなく、「書くのが楽しくなるような自分だけの構成のヒント」を見つけることです。マッピング法は、子どもの自由な発想を大切にしながら、文章の設計図を自然に作り上げていくことができる素晴らしい方法です。
ぜひ、お子さんと一緒に大きな紙を広げ、思いつくままに線と文字を繋げてみてください。きっと、思いもよらない素敵な物語が生まれるはずです。
次回は、「説明文」の構成の考え方についてお話しします。お楽しみに!
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑥~説明文を書くための対話の時間編 – 家庭学習のヒント

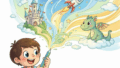

コメント