本日は、子どもの「言葉の力」を育むための言語活動として、学校でもよく行われている「インタビュー」という言語活動についてお伝えします。
第1章:なぜ今、子どもに「インタビュー」をさせるべきなのか?
「インタビュー」と聞くと、テレビや雑誌の記者が行う、少し特別な活動のように感じるかもしれません。しかし、小学校の学習指導要領でも、生活科や総合的な学習の時間の中で、子どもが主体的に探究活動を行う上で、非常に重要な活動として位置づけられています。
なぜ、今の子どもたちにインタビューという言語活動が必要なのでしょうか?
それは、インタビューが「相手意識」を明確にし、すべての言語能力を総合的に高める、最高のトレーニングだからです。
1. 相手意識がモチベーションになる
算数や理科とは違い、インタビューには明確な「相手」がいます。自分が知りたいと思ったことを、相手に直接尋ね、その答えを返してもらう。このリアルタイムなやり取りは、子どもたちの学習意欲を飛躍的に高めます。
「インタビューして終わり」ではありません。聞いたことを整理し、まとめ、それを誰かに伝えるという目的があるからこそ、子どもたちはより深く、主体的に活動に取り組むことができます。
2. 国語のすべての力が育まれる
インタビュー活動は、単に「話す」「聞く」という能力だけでなく、国語科のすべての要素を網羅しています。
- 聞く力:相手の言葉の背景にある意図や感情をくみ取る。
- 話す力:自分の考えを分かりやすく、相手に伝わるように表現する。
- 書く力:聞いた内容を整理し、文章として構成する。
- 読む力:書いた文章を推敲し、より伝わるものへと修正する。
この一連のプロセスは、子どもたちの言語能力を、机上の学習だけでは得られない形で大きく引き上げてくれます。
3. 思考力が育まれる
インタビューの準備段階で、子どもたちは「どうすれば相手のことをもっとよく知ることができるだろうか?」と、深く考えます。この「問いを立てる」という思考プロセスこそが、インタビュー活動の最も価値ある部分です。
私たちはつい、答えを出すことに思考の中心を置いてしまいがちです。しかし、これから子どもたちが生きていく社会は、答えのない問いに満ちています。その答えを探す第一歩である「問いを立てる力」は、将来を生き抜く上で不可欠な能力となるでしょう。
第2章:子どもの好奇心を刺激する「問い」の育て方
では、実際に子どもにインタビューをさせる際、どうすれば効果的に「問いを立てる力」を育めるのでしょうか?
重要なのは、形式的に「質問を考えなさい」と指示するのではなく、「本当に知りたい」という子どもの好奇心を引き出すことです。
1. 「好きな〇〇は?」から始める
インタビューを始める際、最初から難しい質問をする必要はありません。
- 好きな食べ物は何ですか?
- 好きな色は何ですか?
- 好きな動物は何ですか?
こうした質問は、誰もが答えやすく、インタビューの入り口として最適です。まずは、こうした「クローズドクエスチョン(答えが一言で終わる質問)」で、インタビューの雰囲気に慣れさせてあげましょう。
2. オープンクエスチョンで人となりを掘り下げる
いくつかの質問をした後、「オープンクエスチョン(答えが自由な質問)」に切り替えることで、相手の「人となり」を引き出すことができます。
例えば、「好きな食べ物は何ですか?」という質問に対して、「ラーメンです」と答えが返ってきたとします。そこで会話を終わらせるのではなく、次のように掘り下げてみましょう。
- 「どうしてラーメンが一番好きなんですか?」(Why)
- 「どうやってそのラーメン屋さんを見つけたんですか?」(How)
- 「初めて食べた時、どんな気持ちでしたか?」
このように、5W1Hの「Why(なぜ)」や「How(どうやって)」を使うことで、相手はより多くの情報を話してくれます。
「どんな気持ちでしたか?」「それってどういうことですか?」といった質問は、相手の感情や考えを引き出し、単なる事実の羅列ではない、血の通ったエピソードを引き出す上で非常に効果的です。
子ども自身が「もっと知りたい!」と感じる問いを見つけられるよう、こうした質問の切り口を教えてあげましょう。
第3章:書くことで思考が整理される「インタビュー記事」の書き方
インタビューは、話を聞いて終わりではありません。聞いた内容を整理し、文章にまとめることで、子どもの思考はさらに深まります。
1. 音声メモを自分で「文字起こし」する
最近は、AIが自動で音声を文字起こししてくれるサービスも増えました。しかし、小学校のうちは、あえて自分で文字起こしをすることをお勧めします。
なぜなら、音声を聞き直しながら文章を書き出すことで、次のような力が養われるからです。
- 聞く力:話の要点を正確に聞き取る力。
- 構成力:聞いた内容を、どういう順番で書けば分かりやすいかを考える力。
- 思考力:話の内容を改めて振り返り、自分の考えを整理する力。
一見、非効率に思えるかもしれませんが、この手間をかけるプロセスこそが、子どもの言語能力を根底から鍛えてくれます。
2. 「はじめ・中・終わり」の3部構成で書く
インタビュー記事を書く際には、決まった型に沿って書くことで、文章構成力が身につきます。
- はじめ:インタビューした相手の簡単な紹介と、インタビューを始めたきっかけを書く。
- 中:相手の個性がよくわかるような、具体的なエピソードを一つか二つ盛り込む。
- 終わり:インタビューを終えて、自分がどんなことを感じたか、相手からどんなことを学んだかを感想としてまとめる。
第4章:学校を飛び出して、家庭でできる「インタビュー活動」
学校だけでなく、ご家庭でもインタビュー活動は実践できます。
1. 身近な家族にインタビューする
まずは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟など、身近な家族にインタビューしてみましょう。
- 「おじいちゃん、若い頃はどんな夢があったの?」
- 「お母さんの小学校時代は、どんな遊びが流行っていた?」
特に、おじいちゃんやおばあちゃんは、子どもたちにとって教科書には載っていない「生きた歴史」です。戦争のこと、昔の暮らしのことなど、たくさんの貴重なエピソードを聞くことができるでしょう。
もし離れて住んでいる場合でも、ZoomやSkypeといったオンラインツールを活用すれば、顔を見ながら対話ができます。
2. 外部の人に挑戦してみる
少し勇気が必要ですが、子どもが本当に尊敬している人や、関心を持っている分野の専門家に、手紙やメールでインタビューをしてみるのも良い経験になります。
- 釣りが好きなら、釣りの名人に手紙を書いてみる。
- 水族館のシャチが好きなら、飼育員さんにメールを送ってみる。
この活動は、丁寧で失礼のない文章を書く練習になるだけでなく、外部の人と関わることの喜びや、自分の力で世界を広げていく自信にも繋がります。
インタビューは、子どもの聞く力、話す力、書く力、そして考える力を総合的に育む、最高の言語活動です。ぜひ、ご家庭でも実践してみてください。

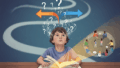
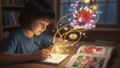
コメント