いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。このブログでは、ご家庭で日々お子さんの教育と向き合っていらっしゃる保護者の方に、少しでもお役に立てる情報を発信したいと思っています。
今回は「説明文の文章構成」について、私のクラスでの実践を交えながら詳しくお話しします。
書く能力を伸ばすためには、もちろんたくさん書くことが大切です。しかし、それと同時に、文章の「型」を学ぶことも非常に重要だと私は考えています。ただ漠然と書き続けるのではなく、書き方をきちんと教えることで、子どもたちの文章力は飛躍的に伸びます。
特に、今回お伝えする説明文の文章構成は、今後のさまざまな場面で役立つ汎用性の高い力です。単に学校の作文の点数を上げるだけでなく、子どもたちの論理的な思考力そのものを育む上で、欠かせない学びとなります。
なぜ今、説明文の構成が重要なのか?
現代の学校教育では、以前にも増して説明文を読む機会が多くなっています。教科書の文章や教材に、事実や情報を論理的に説明する文章が増えていることにお気づきの方も多いのではないでしょうか。これは、自分の意見や考えを、客観的な事実に基づいて論理的に、そして説得力のある形で他者に伝える力が、社会で強く求められているからです。
説明文を学ぶことは、社会に出てからの多くの場面で役立ちます。例えば、大学入試の小論文では、与えられたテーマに対して自分の意見を明確に述べ、その根拠を示す力が問われます。また、就職活動のエントリーシートや企画書、あるいは日々のメールや報告書など、社会に出ると自分の考えを文章で伝える機会は枚挙にいとまがありません。
さらに、この構成の知識は、文章を書く場面だけにとどまりません。面接やディスカッションなど、口頭で自分の意見を述べる際にも、論理的に話を組み立てる力が求められます。相手に分かりやすく、納得してもらえるように話すためには、まず自分の頭の中で考えを整理し、構成を組み立てる必要があります。説明文の構成を学ぶことは、まさにこの思考のトレーニングそのものなのです。
説明文の基本的な構成「序論・本論・結論」説明文の基本的な構成「序論・本論・結論」
説明文には、まず最も基本的な「始め・中・終わり」、あるいは高学年で教える「序論」「本論」「結論」という文章の型があります。これは、家を建てるときの「設計図」のようなものです。しっかりとした設計図があれば、迷わずに文章を組み立てることができます。
この基本の型をさらに効果的にするための、3つの文章構成法を子どもたちに教えています。
双括文(そうかつぶん) この構成は、最初に結論を述べ、次にその根拠を詳しく説明し、最後に再び同じ結論を繰り返す方法です。双括文は、伝えたいことを強調し、読者の理解を確実に深めたいときに最も効果的な「型」であり、最も多く使われる型でもあります。 【構成例】
- 序論(始め): 結論 本論(中): 根拠 結論(終わり): 結論の再提示
- 序論: 旅行に行くなら、私は断然「山」が良いと思います。 本論: その理由は2つあります。まず、山には豊かな自然があり、心が癒されるからです。緑にはリフレッシュ効果があることが科学的にも証明されています。次に、山頂にたどり着いたときに得られる達成感は、何物にも代えがたいからです。 結論: これらの理由から、私は旅行に行くなら山が良いと思います。
頭括文(とうかつぶん) この構成は、最も伝えたいことを文章の最初(序論)に述べ、その後に具体的な根拠や詳細を説明する方法です。 【構成例】
- 序論(始め): 結論 本論(中): 根拠 結論(終わり): まとめ
- 序論: 私は、朝ごはんをしっかり食べることが大切だと思います。 本論: なぜなら、朝ごはんを食べると脳にエネルギーが供給され、午前中の授業に集中できるからです。また、体温が上がり、一日を元気に過ごすことができます。 結論: だからこそ、朝ごはんを毎日欠かさず食べることをおすすめします。
尾括文(びかつぶん) この構成は、最初に問題提起や疑問を投げかけ、読者の興味を引いた後、本文で様々な根拠や事実を提示し、最後に結論を述べる方法です。 【構成例】
- 序論(始め): 問題提起 本論(中): 根拠 結論(終わり): 結論
- 序論: 多くの人が、早起きが苦手だと言います。どうすれば気持ちよく朝を迎えられるのでしょうか? 本論: 早起きには、健康や時間の面で多くのメリットがあります。たとえば、太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜ぐっすり眠れるようになります。また、朝の静かな時間を有効活用すれば、趣味や勉強に集中できます。 結論: このように、早起きは少しの工夫で誰にでもできるようになる、生活を豊かにする習慣なのです。
説得力を高めるための「構成術」
これらの型を使いこなすために、子どもたちには以下の3つのポイントを伝えています。
1. 立場(自分の意見)を明確にする
まず、自分が何を伝えたいのか、立場をはっきりとさせることが最も重要なステップです。例えば、「旅行に行くなら、山と海どちらがいいか」というテーマであれば、まず最初に「私は旅行に行くなら山が良いと思います」と断言します。この「自分の意見」こそが、文章の核となります。この段階で、どちらの立場に立つかを決めなければ、文章全体が曖昧になってしまいます。
2. 根拠を2つ以上用意する
主張を説得力のあるものにするには、しっかりとした根拠が必要です。私は子どもたちに、必ず2つ以上の根拠を考えるように教えています。
先ほどの「山が良い」という主張であれば、根拠として「緑に癒し効果があるから」と「頂上に着いた時に達成感が得られるから」といった具体的な理由を考えさせます。これらの根拠は、単に思いついたことを並べるのではなく、文章のテーマと密接に関連している必要があります。
3. データや反論を盛り込む
説得力をさらに高めるために非常に有効なのが、具体的なデータやグラフを提示することです。たとえば、「山に登ると心拍数が安定し、リラックス効果が高まるという研究結果があります」といった形で、数字や客観的な事実を引用することで、言葉に重みが生まれます。面接など口頭で伝える場合も、「〜というデータがあります」と数字を引用することで、説得力が増します。
また、より高度なテクニックとして、「反論」を予想し、それに対する「反論」を構成に含めることも教えます。これは、読者が抱くであろう疑問を先回りして解決することで、文章全体の信頼性を高める方法です。
例えば、「山よりも海の方が、潮風や波の音で癒される、という人もいるかもしれません。しかし、山には里山のように身近な場所でも行ける場所が多く、手軽に心身をリフレッシュできるというメリットがあります」といった形で、相手の意見を尊重しつつ、自分の意見の優位性を論理的に示す練習をさせます。この反論の反論のプロセスは、子どもたちの思考力を大きく伸ばします。
実践の汎用性:入試や就職活動から英語検定試験まで
この文章構成の型は、さまざまな場面で応用できる汎用性の高い力です。例えば英語検定試験のライティング試験では、与えられたテーマについて英語で自分の意見を述べることが求められます。その構成は、日本語の説明文と全く同じです。
最初に主張を述べ、2つほどの根拠を提示し、最後に結論を繰り返すという型がそのまま通用します。これは面接対策にも非常に役立ちます。面接官からの質問に対し、まず結論を述べ(主張)、その理由を2つほど挙げ(根拠)、最後に結論を繰り返すことで、簡潔かつ説得力のある回答ができるようになります。
このように、説明文の構成を学ぶことは、単に作文が上手くなるだけでなく、論理的に考え、自分の考えを分かりやすく伝える一生の財産となるでしょう。
楽しく学ぶ「対話の時間」
ただ、いきなり「型」に沿って書こうとしても、子どもたちは「面白くない」と感じてしまうかもしれません。そこで、私のクラスでは、作文の時間を「楽しい時間」にするための工夫として、書く前に子どもたちとの「対話の時間」を設けています。
対話を通じて、子どもたちは自分の考えを言葉にする練習ができ、また、友達の考えを聞くことで、新しい視点やアイデアを得ることができます。この対話の時間が、書くことへの意欲を自然に引き出し、文章の「型」を学ぶ土台作りになっていると感じています。
次回は、この「対話の時間」をどのように活用しているのか、具体的な実践例を交えながらお話ししたいと思います。どうぞお楽しみに。
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記①~作家の時間とは? – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記②~子どもの意欲を高める方法 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記③~書き出し編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記④~物語の構成編 – 家庭学習のヒント
【連載】「書くことが好きになる」作家の時間 教室実践記⑤~説明文の構成編 – 家庭学習のヒント


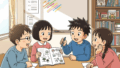
コメント