翻作学習法について
今日は、多くのお子さんがぶつかる壁、「作文が書けない」 「国語が苦手」という悩みについて、一つの解決策を提案したいと思います。
「さあ、思ったことを自由に書いてごらん!」
学校の先生や、お父さん、お母さんからそう言われた時、多くの子どもたちは頭を抱えます。もちろん、スラスラと書ける子もいますが、多くの場合は「何を書いたらいいかわからない…」 「つまらない…」と感じ、国語に苦手意識を持ってしまうきっかけになりがちです。
そこで、今回ご紹介したいのが、翻作学習法です。
これは、オリジナルの文章をいきなり書くのではなく、お手本となる名作の文章構成や表現方法を真似しながら、自分の作品を作っていくという学習法で、日本の国語教育を長年研究されてきた首藤久夫先生(千葉大学名誉教授)が提唱されている学習法です。
この方法は、単なる「お手本を写す」こととは全く違います。それは、国語の力をつける上で、最も効果的で、そして何より子どもたちが「楽しい!」と感じられる、素晴らしい方法なのです。
第1章:「書けない」という壁を乗り越える『翻作』の力
なぜ、子どもたちは「書けない」と感じるのでしょうか?
それは、頭の中に「書くための引き出し」が空っぽだからです。
どこかで見たことのある文章や、心に残った表現、物語の構成など、書くための「材料」がなければ、いくら「自由に書いてごらん」と言われても、文章は生まれてきません。
しかし、翻作学習法は、この「引き出し」を、楽しみながら埋めていくことができます。
1. 学習のハードルがぐっと下がる
「〇〇さんのように、書いてごらん」という、明確な手本があることで、子どもたちは「これなら自分にもできそう!」と感じ、意欲的に取り組めます。
「オリジナル」というプレッシャーから解放される。- 何から始めたらいいかわからない、という不安がなくなる。
名作をベースにするので、書くテーマや構成に悩む必要がなく、書くことに集中できます。
2. 名作の良さを自然と吸収する
翻作のベースとなるのは、教科書に載っているような素晴らしい名作です。その文章構成や言葉選びのセンスを真似ることで、子どもたちは「良い文章とは何か」を肌で感じ、自然と文章の力が養われます。
翻作は、ただの「カンニング」ではありません。それは、優れた技術を学び、自分のものにするための、最も効果的な方法なのです。
3. 個性と創造性が引き出される
「真似」と聞くと、個性がないように思えるかもしれません。しかし、全く同じ作品を真似しても、子どもたちの個性は必ず表れます。
- 着目する視点の違い
- 使う言葉の選び方
- 想像力の広げ方
完成した作品には、子ども一人ひとりの感性が光ります。同じテーマで書かれた友達の作品を読み合うと、その違いに驚き、互いの個性や表現の面白さを認め合うことができます。
第2章:名作を「自分の物語」にする魔法〜『ごんぎつね』から学ぶ実践法〜
翻作学習法は、日本の国語教育を長年研究されてきた首藤久夫先生(千葉大学名誉教授)が提唱されている学習法です。
ここでは、その具体的な実践例を一つご紹介します。
小学校4年生で学習する『ごんぎつね』を題材にした学習です。
多くの学校では、この物語を「あらすじをまとめなさい」といった課題で学習します。しかし、それでは物語の表面的な理解に留まりがちです。
そこで、課題を「ごんぎつねの日記を書こう」に変えてみましょう。
「なぜ、兵十のウナギを盗んだんだろう?」「あの時、ごんはどんな気持ちだったのかな?」「撃たれてしまった時、何を思ったのだろう?」
子どもたちは、ごんの気持ちを想像しながら、物語の本文を何度も何度も読み返します。そして、本文には書かれていない、ごんの心の動きや、その時の情景を想像しながら、日記を書いていくのです。
この活動を通して、子どもたちは次のような力を自然と身につけます。
- 読解力:物語を深く読み込む必要性から、本文の細部にまで目を向けるようになる。
- 想像力:物語の
「行間」を読み、登場人物の感情や思考を想像する力が養われる。 - 書く力:頭の中にあるイメージを、言葉に落とし込む力が鍛えられる。
書くことに苦手意識がある子どもでも、「ごんぎつねの真似をすればいいんだ」と思えるので、安心して取り組むことができます。
また、今ではロイロノートなどのICTツールを使って、子どもたちが書いた日記を簡単に共有できます。友達の作品を読んだ子どもたちは、「ああ、そういう考え方もあるんだ!」 「この書き方、面白い!」と、また新たな刺激を受け、それを自分の作品に取り入れることで、さらに表現の幅を広げていきます。
「友達の真似をしちゃダメだよ!」と言われがちな学校や家庭の指導。しかし、ここでは、「最初は真似していいんだよ」と認めてあげることが非常に大切なのです。
第3章:言葉のセンスが磨かれる『詩の翻作』に挑戦しよう
翻作学習法は、物語文だけでなく、詩や俳句といった表現力を磨く上でも非常に有効です。
詩をいきなり「自由に書いてごらん」と言われても、多くの子どもは戸惑います。しかし、お手本があれば、驚くほどユニークな作品が生まれます。
たとえば、谷川俊太郎さんの詩『生きる』を題材にした学習です。
生きているということ
いま生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみすること
あなたと手をつなぐこと
(谷川俊太郎『生きる』より一部抜粋)
この詩を読み、子どもたちに「生きるということ、それは〇〇ということ」という型で、自由に言葉を埋めてもらうのです。
生きるということ
それは
サッカーでゴールをきめてみんなで喜び合うこと
生きるということ
それは
夕焼け空が今日も見られること
翻作という型があることで、子どもたちは、日頃から感じているささやかなことや、自分なりの哲学を、詩という形で表現する喜びを知ります。
この他にも、翻作学習に適した詩はたくさんあります。
- 工藤直子さんの『のはらうた』より「おれはかまきり」
- おう なつだぜ
- おれは げんきだぜ
- あまり ちかよるな
- おれの こころも かまも
- どきどきするほど
- ひかってるぜ
- この詩のように、短く、力強い言葉で自分の気持ちを表現する練習ができます。例えば、「わたしはかきごおり」や「わたしはセミ」など、別のものになりきって詩を書いてみることで、表現の幅を広げられます。
第4章:学校から家庭へ!親子で楽しむ『翻作』のススメ
翻作学習法は、学校の授業だけでなく、ご家庭でも簡単に取り入れられます。
1. 身近なものを題材にしよう
- 絵本:お気に入りの絵本を読んで、主人公の気持ちを想像しながら、日記や手紙を書いてみる。
- 漫画:好きな漫画のセリフを少し変えて、物語を書いてみる。
2. 親も一緒に楽しもう
「宿題だからやりなさい」というスタンスではなく、お父さんやお母さんも一緒になって楽しむことが、何よりも重要です。
「お母さんは、こんな詩を書いてみたよ」「お父さんも一緒に、主人公の気持ちを考えてみようかな」
親が楽しんでいる姿を見ることで、子どもは「国語って楽しいんだな」という気持ちを自然と持つことができます。
まとめ:国語は「楽しい」と思えることが、一番の才能
翻作学習法は、国語が苦手な子どもでも、「自分にもできる!」という達成感と、「書くって面白い!」という喜びを感じさせてくれます。
この学習法は、単に文章力を高めるだけでなく、他者の表現の面白さを認め、自分の個性を見つけ、そして何よりも、学ぶことの楽しさを子どもたちに教えてくれる、素晴らしい方法です。
国語は、単なる教科ではありません。それは、自分自身を表現し、世界を理解するためのツールです。
これからも、子どもたちの「国語は楽しい!」という気持ちを大切に、このブログで様々なヒントをお届けしていきたいと思います。

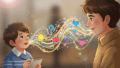
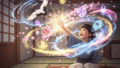
コメント